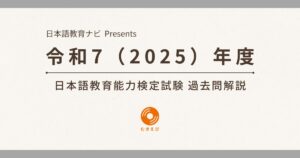令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題14
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 欧州評議会
解説 欧州評議会
本文中に出てくる「ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)」とセットで出題されることが多いです。
解説 ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)
言語能力を「~ができる(Can-do)」の形で表しているのが特徴です。
低い順から
- A1
- A2
- B1
- B2
- C1
- C2
の6段階に分けられており、
- A:「基礎段階の学習者(Basic User)」
- B:「独立した言語使用者(Independent User)」
- C:「熟達した言語使用者(Proficient User)」
として設定されています。
その答えになる理由


「ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)」を発表したのは、「欧州評議会」ですね。
1が正解です。
問2 複言語・複文化主義
その答えになる理由


参考はこちら
出典元は2001年に欧州評議会が発表した資料ですが、英文のため、引用元を参考として記載しています。
欧州共通参照枠(以下『参照枠』)では複言語・複文化主義は以下のように定義されている。
「複言語・複文化主義能力」と言語・文化の流動性、ハイブリッド性
複言語・複文化能力とは、複数の言語を用いる力-ただし力のレベルはさまざま-と、複数の文化の経験とをもつことで、社会的なエージェントとして、コミュニケーションおよび相互文化的インターアクションに参与するための、一個人の能力を指す。そしてこの能力の存在のあり方は、複数の能力が縦列または並列しているのではなく、複雑でより複合的に存在している(Council of Europe,2001,p. 168)。
―「見つめ直そう私の将来と日本語」プロジェクト― P221
佐藤 慎司、柴田 智子
プリンストン大学
複言語・複文化主義において、一個人の能力は、複数の能力が複雑かつ複合的に存在しているとされています。
言い換えれば、一個人の能力は、複数の能力が作用し合って出来上がっているということですね。
2が正解です。
問3 社会的存在
その答えになる理由


参考はこちら
出典元は2001年に欧州評議会が発表した資料ですが、英文のため、引用元を参考として記載しています。
「複言語能力(plurilingual competence)や複文化能力(pluriculturalcompetence)とは、コミュニケーションのために複数の言語を用いて異文化間の交流に参加できる能力のことをいい、一人一人が社会的存在として複数の言語に、全て同じようにとは言わないまでも、習熟し、複数の文化での経験を有する状態のことをいう。この能力は、別々の能力を重ね合わせたり、横に並べたりしたものではなく、複雑で複合的でさえあると考えられる。」
CEFR一般とその増補版で明らかになったことについて P2
京都大学名誉教授 大木 充
4が正解です。
問4 共通参照レベル
その答えになる理由


問1の解説より、CEFRでは言語能力を「~ができる(Can-do)」の形で表し、低い順から
- A1
- A2
- B1
- B2
- C1
- C2
の6段階に分けています。
- A:「基礎段階の学習者(Basic User)」
- B:「独立した言語使用者(Independent User)」
- C:「熟達した言語使用者(Proficient User)」
となっており、各段階を2つずつに分けた3段階・計6レベルの設定ですね。
4が正解です。
問5 ヨーロッパ言語ポートフォリオ
その答えになる理由


参考はこちら
以下、ELPとは「ヨーロッパ言語ポートフォリオ(European Language Portfolio)」のことです。
学習者は、学習の場が正規教育の枠内であろうとなかろうと、言語学習を記録することができる。
国際交流基金
言語学習記録をしていくということは、学習の計画を立て、その学習過程を観察し、学習したことを自己評価していく能力を開発することにつながる。
それは、自己の言語的技能および重要な異文化経験の記録を残す証拠にもなり、また学習で達成したことをファイルしていくこともできる。
学習者にとっては、総括的な言語学習の記録となる。
そして、転校する、進学する、言語コースが始まる、キャリアアドバイザーと会う、就職活動をするといった機会に、自己の言語能力を示すためにELPを提示することができる。
ヨーロッパにおける日本語教育事情とCommon European Framework of Reference for Languages P56
1.4 ヨーロッパ言語ポートフォリオ(European Language Portfolio:ELP)
P56より、1は記載があります。
後述する ELP の3部構成は、教育的機能(pedagogical function)と報告的機能(reporting function)が基盤となっている。
この二つの機能が担う役割は、以下のようにまとめられる。報告的機能
国際交流基金
・公的試験で与えられる言語に関する資格を補足するものとして、ELP所有者の具体的な言語学習経験、外国語の熟練度、到達度を示す
・学校教育内、学外両方の言語学習を記録する
教育的機能
・複言語主義、複文化主義を促進する
・言語学習過程を ELP 所有者に、よりわかりやすく示し、自立学習(learner autonomy)を育成する
ヨーロッパにおける日本語教育事情とCommon European Framework of Reference for Languages P54
1.4 ヨーロッパ言語ポートフォリオ(European Language Portfolio:ELP)
P54より、3は記載があります。
ELPは、欧州評議会の多くの加盟国により、積極的な導入が図られているが、それは以下の二つが主な目的とされている。
国際交流基金
・学習者が、学習段階のどのレベルにおいても、自己の言語的技能を多角的に伸ばしていることを認識し、学習動機がが高められるようにする
・学習者が習得した言語的技能、文化的技能の記録ができるものを提供する
ヨーロッパにおける日本語教育事情とCommon European Framework of Reference for Languages P53-54
1.4 ヨーロッパ言語ポートフォリオ(European Language Portfolio:ELP)
P53-54より、4は記載があります。
記載のない2が不適当です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら