
令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題3D
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


(16)フォーカス
解説 フォーカス
解説 プロソディー(韻律)
解説 プロミネンス
その答えになる理由


本文が小難しく見えるかもしれませんが、内容自体はそこまで複雑ではありません。
(ア)の後ろに例文がありますね。
同じ文でも、
- (申込は70人だったのに)参加者は20人だった
- 参加者は50人未満だった
という2パターンの解釈が考えられることがわかります。
このあとの(17)で聞かれているように、意味的に否定を受ける部分がどこかによって、いずれの解釈になるかが決まります。
ここで否定を受けるのは、文の要素の中で、聞き手が前提としていない新しい情報を伝える部分です。
選択肢の中では「フォーカス」が最も適当ですね。
1が正解です。
否定文におけるフォーカスについては、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。
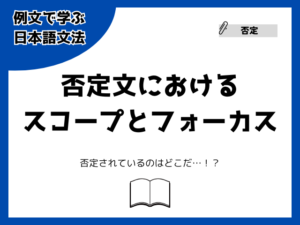
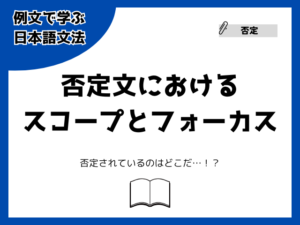
(17)意味的に否定されている部分
その答えになる理由


「(申込は70人だったのに)参加者は20人だった」の場合、下線部Aの例文の中でどこが否定されているかを聞かれています。
- 申込って70人だったよね?何人参加している?
- 50人ドタキャンして、20人しか参加していないよ
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の「講演会に」が否定されるのであれば、「参加していなかった人は、講演会以外のイベントに参加した」ことが示唆されます。
1は間違いです。
2の「50人」が否定されるのであれば、「参加者は50人未満だった」ことが示唆されます。
2は間違いです。
3の「参加している」が否定されることで、「欠席者が50人いた」という下線部Aの解釈が示唆されます。
これが正解です。
4の「50人も参加している」が否定されるのであれば、「参加者は50人未満だった」ことが示唆されます。
4は間違いです。
(18)否定述部と呼応する副詞
せっかくなので、副詞にはどのような種類のものがあるかを整理しておきましょう。
国語学者の山田孝雄は、副詞を「情態副詞」「程度副詞」「陳述副詞」の3つに分類しています。
解説 情態副詞
ゆっくり
じわじわと
などのほか、
擬音語(ピカッと)
擬態語(ガツンと)
畳語(ごろごろ)
なども「情態副詞」に含まれます。
解説 程度副詞
だいぶ
けっこう
かなり
解説 陳述副詞
【推量】「おそらく(~だろう)」
【仮定】「もし(~なら)」
【否定】「けっして(~ない)」
その答えになる理由


「否定述部と呼応」とあるので、陳述副詞の中でも「否定表現と呼応するもの」を選ぶ問題です。
選択肢は全て「~ない」のように否定述部になっているので、肯定述部にできるかを確認していきましょう。
1の「いまだに」は、
○ 彼はいまだに学生だ。
○ 彼はいまだに社会人ではない。
のように、肯定述部・否定述部ともに用いることができます。
2の「ろくに」は、
× 彼はろくに働く。
○ 彼はろくに働かない。
のように、否定述部しか用いることができません。
これが正解です。
3の「本当に」は、
○ 彼女の優しさが本当にうれしい。
○ 彼女の優しさは本当はうれしくない。
のように、肯定述部・否定述部ともに用いることができます。
4の「まだ」は、
○ 彼はまだ学生だ。
○ 彼はまだ社会人ではない。
のように、肯定述部・否定述部ともに用いることができます。
(19)否定述部と呼応するとりたて助詞
その答えになる理由


選択肢に出てくるのは、「しか」「さえ」「すら」の3つですね。
「否定述部と呼応するとりたて助詞」を選ぶので、肯定述部と呼応できるものがないかを見ていきましょう。
「しか」は、
× ここには、彼しか残っている。
○ ここには、彼しか残っていない。
のように、否定述部しか用いることができません。
「否定述部と呼応するとりたて助詞」として、適当です。
「さえ」は、
○ 彼でさえ、この問題が解けた。
○ (いつもは残っている)彼でさえ、残っていない。
のように、肯定述部・否定述部ともに用いることができます。
「否定述部と呼応するとりたて助詞」としては、不適当です。
「すら」は、
○ 彼ですら、この問題が解けた。
○ (いつもは残っているのに)彼ですら、残っていない。
のように、肯定述部・否定述部ともに用いることができます。
「否定述部と呼応するとりたて助詞」としては、不適当です。
「否定述部と呼応するとりたて助詞」として適当なのは、「しか」だけですね。
1が正解です。
(20)取り立て助詞の述部との呼応関係の制約
その答えになる理由


例文を作って考えていきましょう。
限定を表す「ばかり」は、
好きなことばかりするな。
のように、禁止を表す述部と共起することができます。
1は間違いです。
評価を表す「なんか」は、
勉強なんかしない。
のように、否定を表す述部と共起することができます。
2は間違いです。
極限を表す「まで」は、
このゲームは、子どもだけでなく大人まで流行している。
のように、非過去を表す平叙文の述部と共起することができます。
3は間違いです。
例示を示す「でも」は、
○ コーヒーでも飲もうか?
のように、非過去を表す平叙文の述部とは共起することはできますが、
× コーヒーでも飲んだ。
のように、過去を表す述部とは共起しにくいですね。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら












