
令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題8
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 カルチャー・ショック
解説 カルチャー・ショック
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、後半が間違いです。
カルチャー・ショックは誰にでも起こりえるものですが、その程度・期間は人によって異なります。
2は、前半と後半の組み合わせが間違いです。
異文化に対する期待が大きければ、ギャップを感じたときのショックを受けやすく、期待が小ければ、ギャップを感じたときのショックも小さくなります。
3は、何も問題ありません。
これが正解です。
4は、前半が間違いです。
カルチャー・ショックは「異文化を受け入れる過程」で起こるので、「異文化は絶対に受け入れない!」という人の場合はカルチャー・ショックの程度は小さくなります。
問2 ベリー
解説 ベリーによる異文化変容の4タイプ
統合
自文化を保持しながら、新しい文化を取り入れていく態度
同化
自文化の保持をせずに、新しい文化に適応していく態度
分離
自文化を保持し、新しい文化との関わりを避ける態度
周辺化
自文化の保持をせず、新しい文化への適応にも無関心である態度
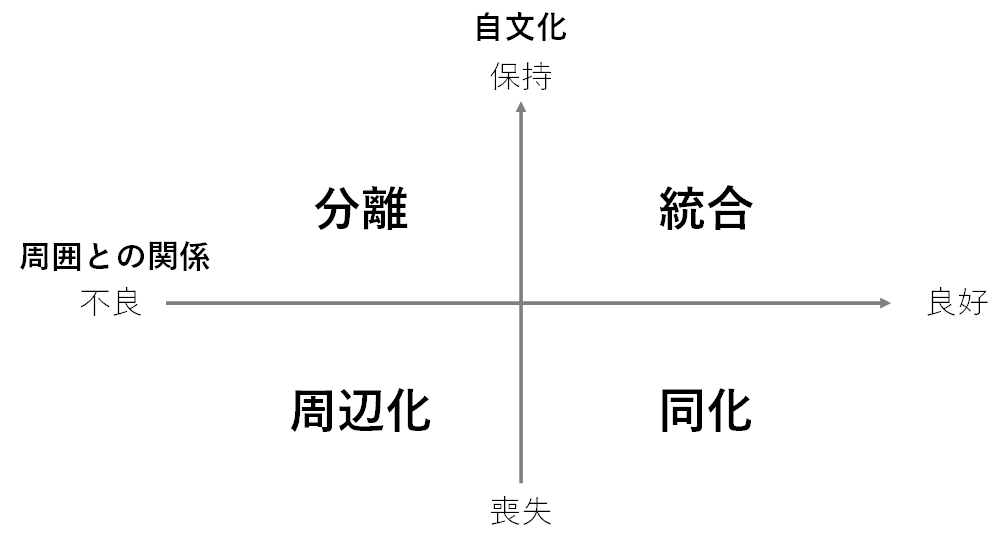
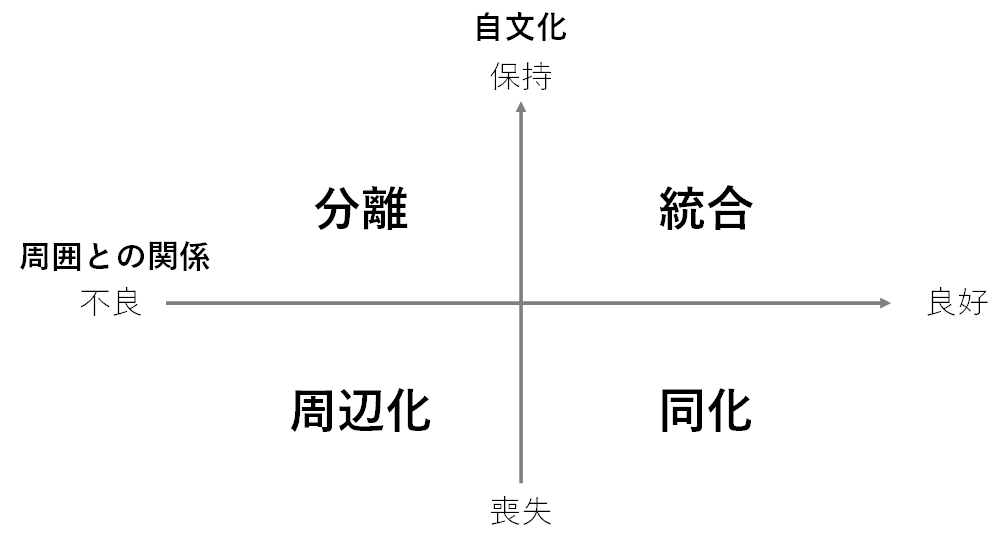
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、周囲との関係は良好ではなく、自文化を引き続き保持しています。
「分離」の態度の例なので、これが正解です。
2は、周囲との関係は良好を目指しており、自文化と距離を置こうとしていますね。
「同化」の態度の例なので、これは間違いです。
3は、周囲との関係・自文化との関係ともに良好を目指しています。
「統合」の態度の例なので、これは間違いです。
4は、周囲との関係・自文化との関係ともに距離を置こうとしていますね。
「周辺化」の態度の例なので、これは間違いです。
問3 アイデンティティ
解説 アイデンティティ
今回はそこまで聞かれていませんが、日本語教育能力検定試験では
- 社会的アイデンティティ
- 個人的アイデンティティ
を区別して出題されることがあります。
併せて、整理しておきましょう。
解説 社会的アイデンティティ
解説 個人的アイデンティティ
解説 アフォーダンス
概念なので、イメージがつきづらいですよね。
公園のベンチ → 座る
子ども時代を過ごした家 → なつかしい
のように、「環境が、行動や感情に影響すること」自体を「アフォーダンス」と言います。
解説 エンパシー
解説 コーピング
休日は、仕事のことを忘れるために趣味に打ち込む
などの行動が該当します。
その答えになる理由


「異文化に接触した際に、どのような態度をとるか?」という異文化受容態度と関わりが深い用語なので、選択肢の中では「アイデンティティ」が良いですね。
1が正解です。
問4 コンテクストの概念
解説 高コンテクスト文化
解説 低コンテクスト文化
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「低コンテクスト文化」では、文脈への依存度が低いため、言葉がそのままの内容で相手に伝わります。
問題が生じた場合は、直接的な対立になりやすいですね。
1は間違いです。
「低コンテクスト文化」では、文脈への依存度が低いため、言葉がそのままの内容で相手に伝わります。
言われたことを文字通りに解釈する傾向が強くなりますね。
2は正しいです。
「高コンテクスト文化」では、文脈への依存度が高いため、話し手・聞き手で共有されているであろう情報をもとに会話をします。
個人が他者から独立した存在だと捉えやすいのは、「高コンテクスト文化」ではなく「低コンテクスト文化」ですね。
3は間違いです。
「高コンテクスト文化」では、文脈への依存度が高いため、話し手・聞き手で共有されているであろう情報をもとに会話をします。
明確に意思を言語化するのは、「高コンテクスト文化」ではなく「低コンテクスト文化」ですね。
4は間違いです。
問5 自己効力感
解説 自己効力感
その答えになる理由


自己効力感を高めて物事に取り組むには、
自分ならできる!やってみよう!
という思考が大切です。
できてもできなくても、ありのままを受け入れよう。
どのような結果になるにせよ、自分の意志で行動することが大事!
現状と目指す姿のギャップを埋めていこう!
という思考は、目標達成する上では非常に大切なのですが、自己効力感とは関係ありません。
選択肢の中では、4が自己効力感を高める内容ですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら












