
令和4年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題3
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 ヲ格の用法
解説 格助詞「を」(ヲ格)の用法
【対象】
文法を勉強した。
【起点】
家を出る。
【経過域】
トンネルを抜ける。
その答えになる理由


自動詞・他動詞の問題ではなく、ヲ格の用法を聞かれているだけですね。
本文に「対象のヲ格をとるのが他動詞」とあるので、対象以外の起点・経過域が当てはまります。
選択肢の内容だと、
- 経路→経過域
- 起点→起点
となるので、3が正解です。
ちなにみ、1・2にある「目的」の用法をもつのは、
- 格助詞「に」(ニ格)
- 格助詞「で」(デ格)
の2つですね。
買い物に出かけた。
ここには、観光で来ました。
などが該当します。
格助詞の用法については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。
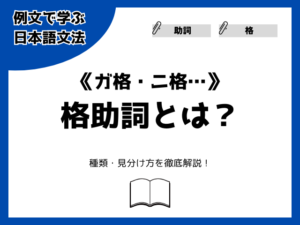
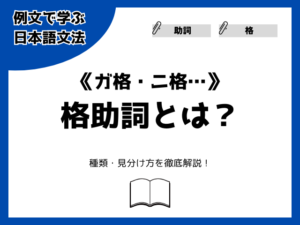
問2 直接受身文
解説 受身文
【能動文】
AさんがBさんを殴った。
【受身文】
BさんがAさんに殴られた。
受身文は、何を主語として表現するかによって、
- 直接受身文
- 間接受身文
- 持ち主の受身文
の3つに分類することができます。
問題で聞かれているのは「直接受身文」だけですが、せっかくなので、3つとも整理しておきましょう。
解説 直接受身文
【能動文】
AさんがBさんを殴った。
であれば、動詞「殴る」の働きかけの対象となる補語が「Bさん」ですね。
「Bさん」を主語にした
【直接受身文】
BさんがAさんに殴られた。
が直接受身文です。
解説 間接受身文
【能動文】
雨が降った。
であれば、「雨が降る」という事態と関連づいた人・物を補完した
【間接受身文】
私は、学校に行く途中で雨に降られた。
が間接受身文です。
解説 持ち主の受身文
「持ち主の受身文」とは、元の能動文の補語として表される物の持ち主を主語として表現する受身文のことです。
【能動文】
AさんがBさんの肩を叩いた。
であれば、動詞「叩く」の働きかけの対象となった「肩」は、Bさんのものですね。
持ち主である「Bさん」を主語にした
【持ち主の受身文】
Bさんは、Aさんに肩を叩かれた。
が持ち主の受身文です。
その答えになる理由


元の能動文の補語となる語が主語になっていれば、直接受身文です。
選択肢の受身文を能動文に変えてみましょう。
【能動文】
友人が私に無理な仕事を頼んだ。
↓
【直接受身文】
私が友人に無理な仕事を頼まれた。
動詞「頼む」の補語は、
- 私に
- 仕事を
の2つです。
そのうちの「私」が主語になっているので、1は直接受身文です。
【能動文】
同僚の鈴木さんが仕事を辞めた。
↓
【間接受身文】
(私が・会社が)同僚の鈴木さんに仕事を辞められた。
受身文の主語になる「私」「会社」は、元の能動文に含まれていないですね。
2は間接受身文です。
【能動文】
5歳下の後輩が先に昇進した。
↓
【間接受身文】
(私が)5歳下の後輩に先に昇進された。
受身文の主語になる「私」は、元の能動文に含まれていないですね。
3は間接受身文です。
【能動文】
映画館で隣の観客が騒いだ。
↓
【間接受身文】
(私は)映画館で隣の観客に騒がれた。
受身文の主語になる「私」は、元の能動文に含まれていないですね。
4は間接受身文です。
問3 「Xが 自動詞」「Yが Xヲ 他動詞」という関係のペア
その答えになる理由


選択肢はどれも、語幹の一部を共有した自動詞-他動詞のペアですね。
- Xが 自動詞
- Yが Xを 他動詞
になっているかを例文で見ていきましょう。
○ 子どもが起きる。
× 母が子どもを起こる。
○ 子どもが起きる。
○ 母が子どもを起こす。
自動詞「起きる」とペアになるのでは、「起こる」ではなく「起こす」ですね。
適切な自動詞-他動詞のペアになっていないので、1は間違いです。
× 私が預ける。
× Aさんが私を預かる。
○ 私がAさんに荷物を預けた。
○ Aさんが私に荷物を預かった。
「預ける」は、対象となる語が必要なので、そもそも自動詞ではなく他動詞ですね。
また、「預かる」も「YがXを」ではなく「~が~に~を」の文型をとるので、設問の内容と合致しません。
2は間違いです。
× 子どもが浴びる。
× 私が子どもを浴びせる。
○ 子どもがシャワーを浴びる。
○ 私が子どもにシャワーを浴びせる。
「浴びる」は、対象となる語が必要なので、そもそも自動詞ではなく他動詞ですね。
また、「浴びせる」も「YがXを」ではなく「~が~に~を」の文型をとるので、設問の内容と合致しません。
3は間違いです。
○ A課長が管理職から下りた。
○ B部長がA課長を管理職から下ろした。
「Xが 自動詞」「Yが Xを 他動詞」のペアになっていますね。
4が正解です。
問4 自動詞と他動詞のペアがある動詞における意味的な違い
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
【静的な動作】
潮が満ちる。
【動的な動作】
海が荒れる。
のように、自動詞の中でも、「静的・動的」が異なります。
また、
【静的な動作】
方針を決める。
【動的な動作】
木をなぎ倒す。
のように、他動詞が表すのは、「状態」ではなく「動作」ですね。
1は間違いです。
【自動詞】
木が倒れる。
【他動詞】
木を倒す。
のように、自動詞・他動詞のどちらも「瞬間的な動作」を表しています。
【自動詞】
木が倒れ続けている。
【他動詞】
木を倒し続けている。
とすれば継続的であることを表すことができますが、この場合が表しているのは「動作」というよりも「状態」ですね。
2は間違いです。
【自動詞】
木が倒れる。
【他動詞】
木を倒す。
のように、
- 自動詞「倒れる」は、立っている→倒れているへの変化
- 他動詞「倒す」は、倒れるという変化の原因となる動作
を表していますね。
3が正解です。
【意志的な動作】
明日は、絶対に7時に起きる。
【無意志的な動作】
雨が降る。
のように、自動詞は「意志的・無意志的」のどちらの場合もあります。
【意志的な動作】
明日は、子どもを7時に起こす。
のように、働きかける対象のある他動詞は、「意志的」な動作のみですね。
4は間違いです。
問5 対応する自動詞・他動詞のペアがなく、文法的な形式で補われる場合
その答えになる理由


自動詞・他動詞で動詞をグループ分けした場合、以下の4つのいずれかになります。
① 自他のペアがある
【自動詞】おもちゃが壊れた。
【他動詞】おもちゃを壊した。
② ペアになる他動詞がない(無対自動詞)
【自動詞】樹が成長する。
【他動詞】×
③ ペアになる自動詞がない(無対他動詞)
【自動詞】×
【他動詞】昇進の話を断った。
④ 自動詞・他動詞を兼ねている(自他動詞)
【自動詞】ついに夢が実現した。
【他動詞】ついに夢を実現した。
②③は、以下の形を用いることで、代替となるペアをつくることが可能です。
② 使役形を用いる
【自動詞】プールで泳ぐ。
【他動詞】プールで泳がせる。
③ 受身形を用いる
【自動詞】ボタンが押された。
【他動詞】ボタンを押した。
対応する自動詞がない場合は「受身形」が、対応する他動詞がない場合は「使役形」がその役割を担います。
1が正解です。
自動詞・他動詞については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。


次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら











