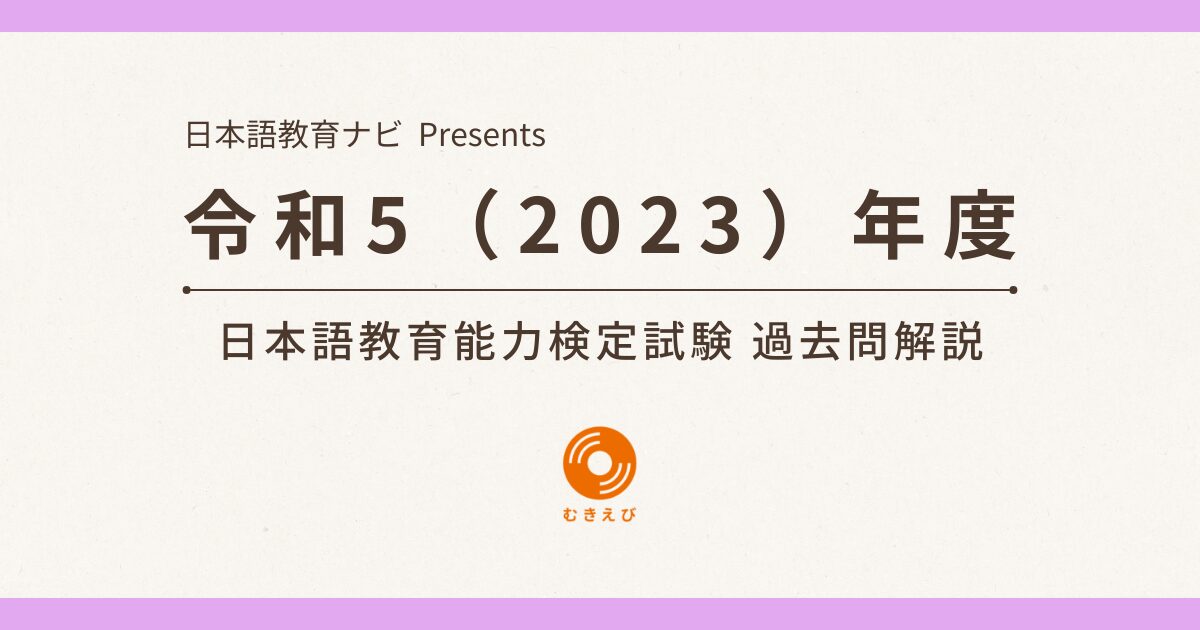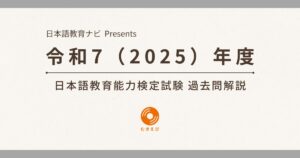令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題3B
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


(6)格助詞「が」の例
その答えになる理由


問題の良し悪しに言及するのは嫌いなのですが、このクオリティはちょっと…。
「格」とは、「名詞と述語の間に成り立つ意味関係」を表す文法用語です。
私が 駅まで 弟を 迎えに 行きます。
には、「が」「まで」「を」「に」の4つの格助詞が含まれています。
それぞれの格助詞の直前を見ると、すべて名詞ですね。
「が」は、動きの【主体】
「まで」は、範囲の終点である【着点】
「を」は、動作の【対象】
「に」は、移動の【目的】
のように、「名詞と述語の間に成り立つ意味関係」を表しています。
選択肢の中で「が」の直前が名詞なのは、1だけですね。
これが正解です。
ちなみに2~4の「が」は、接続助詞です。
後続する内容が先行する内容から推論される内容とは異なる【逆接】として用いられています。
「3は、文の最後にあるのに接続助詞なの…?」となるかもしれませんが、「私はとても面白いと思うが、みんなはそうではないの?」のように、後続する文が省略されているだけですね。
(7)中立叙述の例
その答えになる理由


「中立叙述」という用語に「うっ…!!」となるかもしれませんが、大丈夫です。
本文中で定義されている通り、
・ 文全体を焦点とするのが「中立叙述」の用法
・ その文の焦点となるものを「が」で標示するのが「総記」の用法
です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 Xの発言に対して、「このかばん」が強調されています。
これは「総記」の用法です。
2 Xの発言に対して、「金曜日」が強調されています。
これは「総記」の用法です。
3 Xの発言に対して、「携帯電話」が強調されているわけではないですね。
あくまで「携帯電話がない」という事実を伝えているだけです。
これが「中立叙述」の用法です。
(Yの返答が「え…私が電話を入れるの?」であれば、「総記」の用法です。)
4 Xの発言に対して、「佐藤さん」が強調されています。
これは「総記」の用法です。
3が正解です。
(8)文や節・句における格助詞「が」の使い方
その答えになる理由


例文を作って考えてみましょう。
AさんがBさんに殴られた。
動作主は、述語から判断します。
「殴る」という動作をしたのは、Bさんですね。
「Bさんに」となっているので、受身文では、動作主を「に」で標示することがわかります。
1は間違いです。
ちなみに、「BさんがAさんを殴った」のような能動文の場合は、動作主は「が」で標示されます。
AさんがBさんに残業させた。
残業を指示したのはAさんで、残業させられたのはBさんですね。
使役者がAさん・被使役者がBさんです。
「Bさんに」となっているので、使役文では、被使役者を「に」で標示することがわかります。
2は間違いです。
① 彼が私の婚約者です。
↓ ガ格名詞である「彼が」をそのまま主題化すると…
② 彼がは私の婚約者です。
「句」とは、単語2つ以上から成るまとまりで、主語+述語になっていないもののことです。
(単語2つ以上から成るまとまりで、主語+述語になっているものは「節」と言います。)
「名詞句」とは、句の中でも名詞と同じ役割ができるもののことです。
今回は「ガ格名詞句」なので、格助詞「が」を含むものですね。
例文での「ガ格名詞句」は、「彼が」です。
①→②のように「は」に前接させて主題化すると………不自然ですね。
「ガ格名詞句」は、そのまま「は」を付加して主題化することはできず、
彼は私の婚約者です。
のように、「が」を取り除く必要があります。
3は間違いです。
③ 私が昨日食べたものは、シロノワールです。
↓ 「が」を「の」に置き換えてみると…
④ 私の昨日食べたものは、シロノワールです。
「節」とは、単語2つ以上から成るまとまりで、主語+述語になっているもののことでしたね。
「名詞修飾節」なので、「主語+述語」の形で名詞を詳しく説明しています。
例文での「名詞修飾節」は、「私が昨日食べた」です。
③→④のように「が」を「の」に置き換えてみると………文が成立しますね。
置き換えられないパターンもいくつかあるのですが、今回は「置き換えられることがある」なので、選択肢の内容に問題はありません。
4が正解です。
(9)「が」を用いるべきところに「は」を用いる誤用
その答えになる理由


この問題は、正解を選ぶために「複文」の知識が、不正解を裏付けるために「助詞」の知識が必要になります。
解説が長くなりますが、超重要な分野なので、ぜひお付き合いください。
まずは、下線部Dの例文を見ていきましょう。
① 太郎は帰ってきたら、(私たちは)夕食にしよう。
② 太郎が帰ってきたら、(私たちは)夕食にしよう。
①が元の間違っている文・②が正しい文です。
わかりやすいように、後半に動作主を付け加えました。
このように、節(述語を中心とするまとまり)を2つ以上もつ文を「複文」と言います。
(節を1つだけもつ文は、「単文」です。)
②の文であれば、「(私たちは)夕食にしよう」のようなメインとなる節を主節・「太郎が帰ってきたら」のようなサブとなる節を従属節と言います。
今回は、なぜ①の「は」はNGで・②の「が」はOKなのか?を見ていくのですが、それには「従属節の従属度」の知識が必要です。
「従属節」は、その名の通り、主節に付き従っています。
どれくらい付き従っているかには程度があり、その度合いを「従属度」と呼んでいます。
単文であれば持っている要素が多い場合は、主節に対する従属度は低いです。
少ない場合は、主節に対する従属度が高くなります。
イメージがつきにくいと思うので、例文を使って見ていきましょう。
1) 従属度が高い従属節
従属度が高い従属節では、単文であれば当然もっている要素が欠落しており、その要素を主節に依存しています。
Aさんが音楽を聴きながら勉強している。
主節は「Aさんが勉強している」・従属節は「音楽を聴きながら」です。
従属節には、文であれば必要なはずの「主語」がありません。
主語を主節に依存しているので、従属度が高い従属節だと言えます。
2) 従属度が中程度の従属節
従属度が中程度の従属節では、単文がもっている要素のいくつかは現れ、いつくかは主節に依存しています。
従属節が高い従属節では省略されていた「主語」が現れるのが特徴です。
雨が降り出したのに、審判は試合を続行した。
主節は「審判は試合を続行した」・従属節は「雨が降り出したのに」です。
従属節にも主語があり、先ほどよりも従属度が下がっていることがわかると思います。
「雨が降り出したのに」は自然だけど、「雨は降りだしたのに」だと不自然だよね…?と気づいた方はさすがです。
従属度が中程度の従属節では、「が」による主語は現れても、「は」による主題は現れることができません。
3) 従属度が低い従属節
従属度が低い従属節では、主節とは独立した文法的要素をもつことができます。
「主語」のみならず、「主題」も現れます。
勉強は大変ですが、(私は)頑張っています。
主節は「(私は)頑張っています」・従属節は「勉強は大変ですが」です。
従属節に主題が現れ、さらに従属度が下がっていることがわかると思います。
この場合は、「勉強は大変ですが」「勉強が大変ですが」のどちらでも自然な文ですね。
ここまでの内容で問題の要点になるところをまとめると
従属度が低い従属節…「が」「は」のどちらもOK
従属度が中程度の従属節…「が」のみOK
となります。
下線部Dの例文をもう1度確認してみましょう。
① 太郎は帰ってきたら、(私たちは)夕食にしよう。
② 太郎が帰ってきたら、(私たちは)夕食にしよう。
①がNG・②がOKなのは、従属節の従属度の問題であることがわかると思います。
①は、従属度が中程度なのに、主題の「は」が現れている誤用ですね。
②のように、「が」にしないと不自然です。
この例と同じ原因による「は」の誤用を探してみると…4が正解ですね。
従属度が中程度なのに、主題の「は」が現れている誤用です。
ここまでが、正解を探すための「複文」の知識です。
ここからは、不正解を裏付けるための「助詞」について解説していきます。
「が」は格助詞・「は」は取り立て助詞です。
1) 「が」は中立叙述の用法があるが、「は」にはない
(6)で出てきた「中立叙述」は、「は」「が」の違いを説明するときによく出てきます。
「が」には中立叙述の用法がありますが、「は」にはありません。
中立叙述は、「文全体を焦点とする(=主題がない)」ものだからです。
外を歩いていて、急に天気が悪くなってきたときに
○ 雨が降ってきた。
は自然ですが、
× 雨は降ってきた。
だと不自然ですよね。
このような目の前の出来事には、中立叙述の用法を持つ「が」の方が適しています。
選択肢1は、中立叙述の内容なのに「は」を用いている誤用です。
2) 「が」は排他の用法があるが、「は」にはない
「排他」とは、「他のどれでもなく、コレ!」のことです。
文法の中で、どの分野が1番好き?
という質問に対して、
○ 複文が1番好き!
は自然ですが、
× 複文は1番好き!
だと不自然ですね。
「複文が」だと「格・モダリティのような他の分野ではなく」ということがわかりますが、「複文は」だと「複文は好きなんだけど、他の分野はそこまで…」のように、質問と答えが噛み合っていません。
選択肢2・3は、排他の内容なのに「は」を用いている誤用です。
(10)省略され得る格助詞
その答えになる理由


ここで出てきている格助詞は、「を」「と」「に」「で」「へ」の5つですね。
「に」「で」「へ」は、着点・方向の用法に限定されています。
「に」「で」は用法が多くて、全部だと検証が大変だからでしょうか…?
「を」「と」は、用法が限定されていないので、早々に省略できる用法が見つからなければ、順に検証していかなければなりません。
例文で考えてみましょう。
【対象】の用法
何をしたの⁉
→ ○ 何したの⁉
ちょっと、水をこぼしちゃって…
→ ○ ちょっと、水こぼしちゃって…
のように、話し言葉では「を」を省略することができます。
【相手】の用法
彼氏とケンカをした。
→ × 彼氏ケンカした。
【着点】の用法
氷が溶けて水となった。
→ × 氷が溶けて水なった。
【内容】の用法
Aさんは親友と呼べる。
→ × Aさんは親友呼べる。
のように、話し言葉では「と」を省略することができません。
「に」の用法の中で、「着点・方向」に関わるものは1つだけです。
【着点】の用法
どこに行ってきたの?
→ ○ どこ行ってきたの?
図書館に行ってきた。
→ ○ 図書館行ってきた。
のように、話し言葉では「に」を省略することができます。
「で」の用法の中で、「着点・方向」に関わるものは1つだけです。
【場所】の用法
図書館で勉強している。
→ × 図書館勉強している。
のように、話し言葉では「で」を省略することができません。
「へ」には、着点(移動の方向)の用法しかありません。
【着点】の用法
図書館へ行ってくる。
→ ○ 図書館行ってくる。
のように、話し言葉では「へ」を省略することができます。
省略できるものは、「を」「に」「へ」ですね。
2が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら