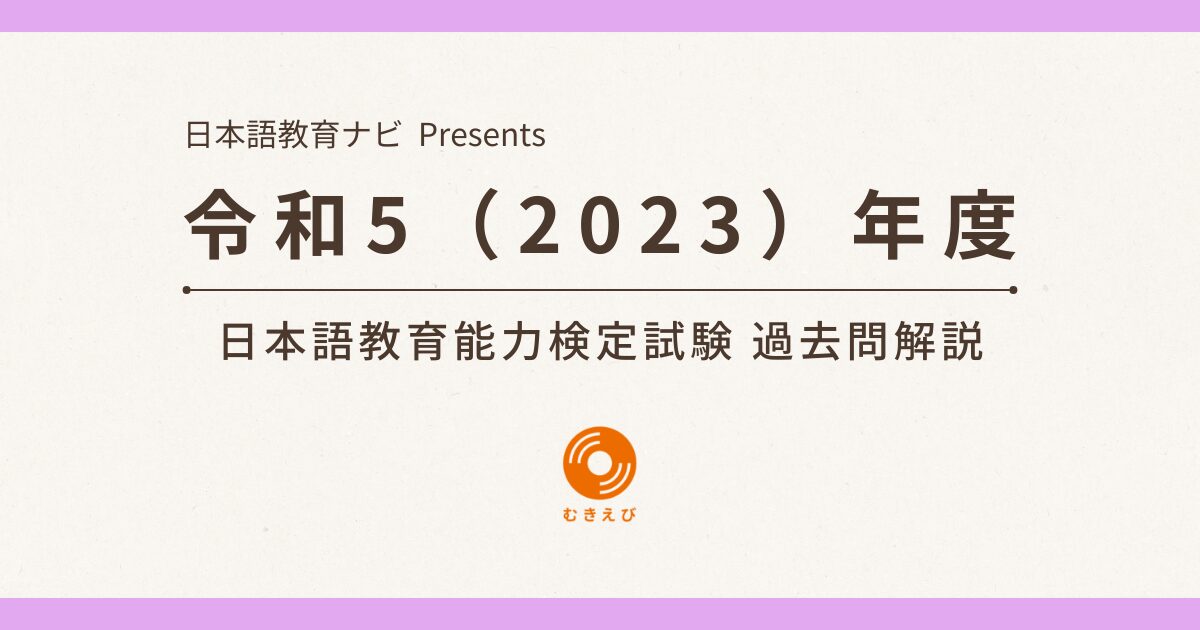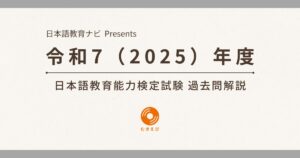令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題6
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 内容重視の指導法(CBI)
解説 Content-based Instruction(CBI)
教科学習では、数学の授業を目標言語で行う…などがCBIを取り入れた授業例です。
- 各課ごとに「教科の目標」と「言語の目標」を設定し、言語指導では教科学習に必要な語彙や表現とあわせて「学習スキル」を養成を図る。
- 4技能を統合的に取り入れる。
- 評価基準にルーブリックを活用する。
- 活動時の発問は、証拠の裏付けをしながら論理的に述べる本質的な内容が重視される。
- これらを協同学習の場で身につける。
といった特徴があります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、オーディオ・リンガル・メソッドの内容を取り入れた授業例だと思います。
文法規則の説明を目標言語で行っていればCBIを取り入れていますが、この内容だと単なる外国語教育ですね。
2は、コミュニティ・ランゲージ・ラーニング(CLL)を取り入れた授業例だと思います。
「コミュニティ・ランゲージ・ラーニング」とは、教室内において「他の学習者の前で間違えることへの不安」を和らげるために、カウンセリングのやり方を応用した教授法のことで、学習者がわからない部分があったときに教師が補助を行います。
3は、「言語形式とそれが使われる文脈を切り離さずに捉えて」が小難しいですね。
CBIでは教科(1+1=2)と言語(one plus one equals two)を「これは数学の内容・英語の内容」のように区別することはありません。
言語形式(one plus one equals two)とそれが使われる文脈(1+1=2)を切り離さずに教えていくので、3が正解です。
4は、サイレント・ウェイを取り入れた授業例だと思います。
「サイレント・ウェイ」では、「真の習得は学習者の気づきなしでは起こらない」という考えのもと、教師は沈黙し、学習者が試行錯誤の上で規則や法則を発見して学ぶことを支援することが特徴です。
問2 イマージョン教育
解説 イマージョン教育(イマージョン・プログラム)・サブマージョン教育(サブマージョン・プログラム)
反対の言葉は「サブマージョン教育(サブマージョン・プログラム)」と言います。
少数言語話者を多数言語の環境に入れて、その中で言語を学んでいく学習形態です。
「イマージョン教育」よりも、同化主義の色が強くなります。
解説 取り出し授業・入り込み授業
反対の言葉は「入り込み授業」と言います。
一斉授業の中に入り、補助が付き添う形で学習を支援します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「支援者が横に付く」「目標言語の母語話者と同じ授業を受ける」は、入り込み授業の内容ですね。
1は間違いです。
「目標言語が話せない」「目標言語の母語話者のクラスに入る」は、サブマージョン教育の内容ですね。
2は間違いです。
「特定の授業」「在籍クラスとは別の場所に通級」は、取り出し授業の内容ですね。
3は間違いです。
「理科・数学などの教科を」「目標言語で学ぶ」は、イマージョン教育の内容ですね。
4が正解です。
問3 内容言語統合型学習(CLIL)
解説 内容言語統合型学習(CLIL)
「 内容言語統合型学習(CLIL)」 では、
- Content(内容)
- Communication(言語知識・言語使用)
- Cognition(思考)
- Community/Culture(協学・異文化理解)
の4つの要素を取り入れて教材開発や指導をすることで、教育の質が高くなると考えられています。
基本は目標言語だけの授業ですが、学習者が困っている場合は部分的に媒介語を使用してしっかり支援するといった柔軟性も持ち合わせています。
その答えになる理由


これは、内容言語統語型学習(CLIL)の内容を知っているかだけですね。
2が正解です。
たまに出題されるのですが、細かい内容には触れられずに、4つのCの内容だけが問題になります。




問4 スキャフォールディング
解説 最近接発達領域(ZPD)
「できない」から「できる」には、その中間の段階があるとしており「最近接発達領域」「発達の最近接領域」と呼んでいます。
- 外言 … 相手に何かを伝えるコミュニケーションのための言語
- 内言 … 自分の頭の中で、思考を組み立てるための言語
- スキャフォールディング … 「できない」から「できる」に至る上での支援・手助け
がキーワードで、子どもの言語発達をこれらの概念を使って分析しています。
その答えになる理由


私は、↓の赤字のように考えて3を選びました。
公式解答を見て出題意図が理解できたので、改めて解説します。
(どのように間違えたか?を見てほしいので、過去の内容を赤字で残しておきます。)
よくよく選択肢を読んだら、消去法で1が正解ですね。。
「スキャフォールディング」は、「できない」から「できる」に至る上での支援・手助けのことです。
「足場掛け」と訳されることもあり、誰かに少しだけ手伝ってもらうことで、あることができるようになります。
「環境を整えておいたよ!」ではなく、「できるように、ちょっとだけ引き上げるね!」が適切です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
2は、学習者本人に直接関わることではなく、周囲の環境を整えているだけですね。
これは、スキャホールディングに関する指導法として適当ではありません。
3は、学習者本人に関わっていますが、引き上げる内容ではなく、環境を整えているだけですね。
これは、スキャホールディングに関する指導法として適当ではありません。
4は、学習者本人に関わっていますが、引き上げる内容ではなく、環境を整えているだけですね。
これは、スキャホールディングに関する指導法として適当ではありません。
残った1が正解です。
当初の解説内容
↓ここから
「スキャフォールディング」は、「できない」から「できる」に至る上での支援・手助けのことです。
「足場掛け」と訳されることもあり、誰かに少しだけ手伝ってもらうことで、あることができるようになります。
環境を整えるだけでなく、具体的な支援が期待できるかがポイントですね。
選択肢を見てみると…
1・2・4は、環境を整えているだけで、実際に誰かが具体的な支援してくれるわけではないですね。
「スキャフォールディング」の指導法ではないので、これらは間違いです。
3は、「目標言語を使う人」という具体的な支援者が登場しています。
これが正解です。
問5 タスク中心の教授法の特徴
解説 タスク中心の教授法
タスクを達成するための行動の中で、フォーカス・オン・フォームに基づき、学習者が目標言語を積極的に使うことで自然なコミュニケーション能力を身に着けることを促していきます。
解説 フォーカス・オン・フォーム(FonF)
言語学者のロングは、コミュニケーションを進める中で、お互いの発話意図を理解し合えるように工夫する対話である「意味交渉」を行うことで、「フォーカス・オン・フォーム」が促されると説明しています。
「意味のやり取り」と「言語の形式」、両方を重視するのが特徴です。
以下、関連する用語もあわせて整理しておきましょう。
解説 フォーカス・オン・フォームズ(FonFs)
代表的な教授法は、「オーディオリンガル・メソッド」です。
解説 フォーカス・オン・ミーニング(FonM)
代表的な教授法は、ナチュラル・アプローチやコミュニカティブ・アプローチです。
その答えになる理由


私は、↓の赤字のように考えて1を選びました。
公式解答を見て出題意図が理解できたので、改めて解説します。
(どのように間違えたか?を見てほしいので、過去の内容を赤字で残しておきます。)
もっと本質的に考えなければならない問題でした。。
2と3が間違いである理由は、当初の解説内容から変更ありません。
タスク中心の教授法は、「フォーカス・オン・フォーム」に基づいています。
「フォーカス・オン・フォーム」では、
・ 意味のやり取り
・ 言語の形式
の両方を重視しているのが特徴です。
「言語形式に焦点を当てながら」だと不十分なので、2は間違いです。
タスクの難易度は、
△ タスク達成のために使用する語彙と文型
ではなく
◎ タスクそのものの内容
で決まります。
「使用する表現が難しいから、タスクが難しい」のではなく、「タスクが難しいから、そこで使う表現も難しい」ですね。
3は間違いです。
当初正解だと思った1は、後半が間違いでした。
指導の焦点は、タスクのプロセスでも、そのタスクを達成できたかという結果でもないですね。
大切なのは、タスクによって、目標としていた言語能力を身につけられたかです。
当初4を間違えだと思ったのは、考え方の視座が低かったことが原因でした。
「学習者のニーズに合わせてタスクを設定」というのは、タスク中心の教授法による指導を行う中で出てきた考えの1つであり、学習者中心であるかは各研究者の中でも意見が割れている部分です。
学習者中心でも・教師中心でも良いので、4が正解です。
当初の解説内容
↓ここから
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は何も問題ないですね。
これが正解です。
「タスク中心の教授法」とは、学習者のニーズに合わせたタスクを中心とし、それタスク遂行の過程において言語習得させていく教授法ですが、重視されるのは「タスクが完了したか?」という結果です。
そのため、目標としていた表現の定着まではできず、言い換えた簡単な表現であったり、片言で終わってしまったりした…ということもありえます。
タスク中心の教授法は、「フォーカス・オン・フォーム」に基づいています。
「フォーカス・オン・フォーム」では、
・ 意味のやり取り
・ 言語の形式
の両方を重視しているのが特徴です。
「言語形式に焦点を当てながら」だと不十分なので、2は間違いです。
タスクの難易度は、
△ タスク達成のために使用する語彙と文型
ではなく
◎ タスクそのものの内容
で決まります。
「使用する表現が難しいから、タスクが難しい」のではなく、「タスクが難しいから、そこで使う表現も難しい」ですね。
3は間違いです。
「タスク中心の教授法」とは、学習者のニーズに合わせたタスクを中心とし、それタスク遂行の過程において言語習得させていく教授法のことです。
教師の指導の目的に基づいてタスクが決まるわけではないので、4は間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら