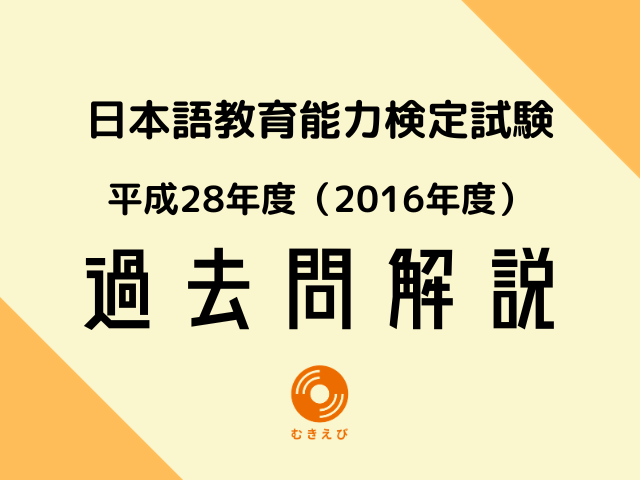平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題4
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 コミュニカティブ・アプローチ
「コミュニカティブ・アプローチ」は外国語教授法における重要単語です。
用語の意味だけでなく、問2のように具体的な内容を聞かれることもあるので、しっかりと押さえておきましょう。
解説 コミュニカティブ・アプローチ
「コミュニカティブ・アプローチ」とは、コミュニケーション能力の獲得・養成を目標として外国語教授法の総称のことです。
文法や文型の反復練習中心である「オーディオ・リンガル・メソッド」への批判から発展しました。
その答えになる理由


外国語教授法は用語が多いので、問題になるときは「誤答の選択肢が別の教授法の説明」になっていることが多いです。
1つずつ確認していきましょう。
1は「初期段階は理解優先」「目標言語で発言することへの…」なので、「ナチュラル・アプローチ」の内容です。
「ナチュラル・アプローチ」では、「意味に焦点を当てて聴解を行う」「学習者が自然に話し出すまでは発話を強制しない」「学習者の発話に誤りがあっても不安を抱かせないために直接的な訂正は行わない」などの特徴があります。
2は「目標言語の音声や文法を習慣づける」なので、「オーディオ・リンガル・メソッド」の内容です。
「オーディオ・リンガル・メソッド」では、「パターン・プラクティス」などの反復練習に特徴があります。
3は「学習者自らが帰納的に文法規則を見つける」なので、「サイレント・ウェイ」の内容です。
「サイレント・ウェイ」では、「真の習得は学習者の気づきなしでは起こらない」という考えのもと、教師は沈黙し、学習者が試行錯誤の上で規則や法則を発見して学ぶことを支援することに特徴があります。
4は「会話の中での意味交渉」なので、「コミュニカティブ・アプローチ」の内容です。
これが正解です。
「意味交渉」という用語は、外国語教授法の分野でよく出てきます。
「言っていることがお互いに理解できるように工夫するコミュニケーション」のことです。
外国語教授法は、以下に練習問題を掲載しています。
ぜひ、チャレンジしてみてください。
↓ 用語の一問一答


↓ 流れの理解


問2 コミュニカティブ・アプローチによる指導
「コミュニカティブ・アプローチ」は、コミュニケーション能力の獲得・養成を目標とした外国語教授法の総称です。
「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく伸ばして、コミュニケーション能力を伸ばすことが重視されており、具体的な教室活動は以下のようなものが挙げられます。
解説 インフォメーション・ギャップを利用した活動
「インフォメーション・ギャップ」とは、話し手と聞き手の間に存在する情報量の差のことです。
「インフォメーション・ギャップ」を利用した活動では、会話の参加者同士が既にわかっていることを質問し合うのではなく、会話の参加者それぞれに異なる情報を与えて、本人が持っていない情報を他の人に質問して聞き出すことなどをしていきます。
解説 チョイスを利用した活動
「チョイス」とは、実際のコミュニケーションにおいて会話の参加者が持っている「選択の自由」のことです。
話し手は話す内容や表現の仕方を自由に選択しながら自分の話を進め、聞き手は相手が何を話すのかを常に意識しながら聞いています。
教室活動においても、「どのような情報をどのような順番で相手に提供するか」「どのような情報を聴き取るのか」は学習者自身に選択権があるような内容を組み込むことによって、実際のコミュニケーションに近い練習をすることができます。
その他、選択肢に出てくる用語を先に確認しておきましょう。
解説 否定証拠
「否定証拠」とは、文法的に「間違いである」という証拠のことです。
教室内では誤った文法だと訂正してもらえますが、実際のコミュニケーションだと意味さえ通じれば訂正されないことが多いですね。
後者の場合は、「否定証拠が示されていない」と言えます。
解説 真正性 オーセンティシティ
「真正性」とは、外国語教育で用いられる教材や教室活動等が「実際の言語の運用状況をどの程度まで反映できているか」という観点のことです。
「オーセンティシティ」とも言います。
「タスク中心の教授法」等でも出てくる用語ですね。
「タスク中心の教授法」では、教材等が実際の社会で使われているものかどうかという表面的なものだけでなく、内容や使い方も実際の言語使用状況に合っている活動かどうかも重視されています。
その答えになる理由


「コミュニカティブ・アプローチでの言語活動を行う際に必要でない条件のもの」を選ぶ問題です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
実際のコミュニケーションにおいて、「この文法、間違っていますよ」と訂正されることはあまりありません。
意味さえ通じればOKなので、対話の相手から「否定証拠」を与えられることは少ないですね。
1が正解です。
2は「チョイス」の内容
3は「インフォメーション・ギャップ」の内容
なので、間違いではありません。
4のように、対話者間のやり取りに真正性があること(=実際の使用状況に合っていること)はコミュニケーションを重視するコミュニカティブ・アプローチにおいて重要な要素です。
4は間違いではありません。
問3 タスク中心の教授法
解説 タスク中心の教授法
「タスク中心の教授法」とは、学習者のニーズに合わせたタスクを中心とし、それタスク遂行の過程において言語習得させていく教授法のことです。
タスクを達成するための行動の中で、フォーカス・オン・フォームに基づき、学習者が目標言語を積極的に使うことで自然なコミュニケーション能力を身に着けることを促していきます。
解説 フォーカス・オン・フォーム FonF
「フォーカス・オン・フォーム(FonF)」とは、ロングが提唱した、コミュニケーション活動を重視するが、意味の理解ややり取りだけでなく、そこで用いられる音声・語彙・文法などの言語の形式にも焦点を当てる概念のことです。
対照的な用語は「フォーカス・オン・フォームズ(FonFs)」です。
解説 フォーカス・オン・フォームズ FonFs
「フォーカス・オン・フォームズ(FonFs)」とは、コミュニケーションや意味理解は軽視され、特に文法を中心とした言語の形式面に注目する概念のことです。
代表的な教授法は、「オーディオ・リンガル・メソッド」です。
その答えになる理由


「タスク中心の教授法」は「フォーカス・オン・フォーム」に基づいています。
4だけが「フォーカス・オン・フォームズ」の内容ですね。
これが正解です。
問4 コミュニケーション・ストラテジー
まずは、用語から確認していきましょう。
解説 コミュニケーション・ストラテジー
「コミュニケーション・ストラテジー」とは、相手の言ったことがわからなかったとき・自分の言ったことが伝わらなかったときの修復の仕方のことです。
解説 回避
「回避」とは、「コミュニケーション・ストラテジー」の1つで、難しい文法形式を使わずに簡単な言い方をすること等、ある語・用法を避けることです。
解説 言い換え
「言い換え」とは、「コミュニケーション・ストラテジー」の1つで、類似表現を使ったり新しい語を作ったり等、ある語を別の単語で言うことです。
解説 母語使用
「母語使用」とは、「コミュニケーション・ストラテジー」の1つで、目標言語での言いたい語がわからなかった場合に自分の母語を使用することです。
解説 援助要求
「援助要求」とは、「コミュニケーション・ストラテジー」」の1つで、わからない部分を聞き返したり、辞書の使用を求めたりすることです。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 「コミュニケーション・ストラテジー」における「言い換え」の内容です。
2 「コミュニケーション・ストラテジー」における「回避」の内容です。
3 「コミュニケーション・ストラテジー」における「母語使用」の内容です。
残った4が正解です。
4の内容は「言語学習ストラテジー」における「情意ストラテジー」の内容です。
「言語学習ストラテジー」も頻出分野なので、合わせて整理しておきましょう。
解説 学習ストラテジー
「学習ストラテジー」とは、学習を進める上で個人がとる方法のことです。
大きく「直接ストラテジー」「間接ストラテジー」に分けられます。
解説 直接ストラテジー
「直接ストラテジー」とは、学習ストラテジーのうち、学習に直接影響を与えるものを言います。
大きく「記憶ストラテジー」「認知ストラテジー」「補償ストラテジー」に分けられます。
● 記憶ストラテジー
記憶を定着させるために取る方法のことです。
語呂合わせや、繰り返し音読する等が該当します。
● 認知ストラテジー
言葉と言葉を関連づけたり、より大きな枠で取られるなと、認知的な理解を促進させる方法のことです。
教科書の内容をノートに自分の言葉でまとめる等が該当します。
● 補償ストラテジー
前後の文脈や背景知識を使って、言語の知識不足等による理解の支障を補っていく方法のことです。
解説 間接ストラテジー
「間接ストラテジー」とは、学習ストラテジーのうち、学習の環境を整えたり、学習へのモチベーションを保ったりと、間接的に学習を支えるものを言います。
大きく「メタ認知ストラテジー」「情意ストラテジー」「社会的ストラテジー」に分けられます。
● メタ認知ストラテジー
自分自身の学習状況について客観的に観察し、把握するための方法のことです。
自身の得意・不得意を把握して学習計画を立てる等が該当します。
● 情意ストラテジー
自分の精神的な安定を保つためにとる方法のことです。
発表前に気持ちを落ち着かせる等が該当します。
● 社会的ストラテジー
人間社会や環境を利用する方法のことです。
母語話者の友人に質問したり、図書館で勉強したりする等が該当します。
問5 内容言語統語型学習(CLIL)
解説 内容言語統語型学習(Content and Language Integrated Learning)
「内容言語統語型学習(CLIL)」とは、Content(科目内容)・Communication(言語力)・Cognition(思考力)・Community(協同学習)の4つの要素をバランスよく育成することを目的とした教授法のことです。
その答えになる理由


2の「内容」「言語」「思考」「協学」が4つのCそのままですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら