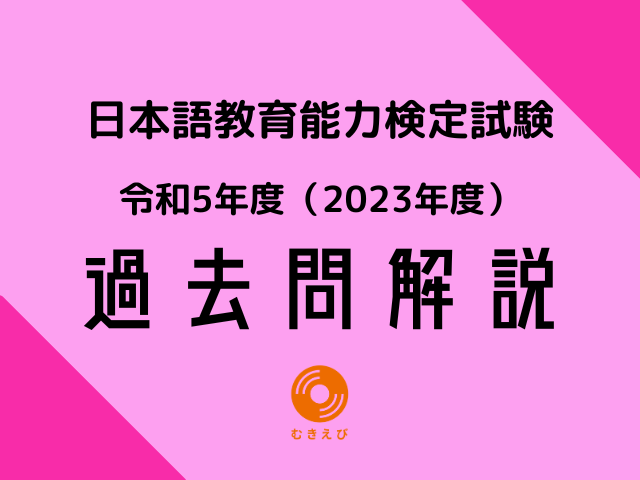令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題10
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 学習ストラテジー
解説 学習ストラテジー
大きく
- 直接ストラテジー
- 間接ストラテジー
に分けられます。
解説 直接ストラテジー
大きく
- 記憶ストラテジー
- 認知ストラテジー
- 補償ストラテジー
に分けられます。
解説 記憶ストラテジー
語呂合わせ
繰り返し音読する
などが該当します。
解説 認知ストラテジー
教科書の内容をノートに自分の言葉でまとめる
などが該当します。
解説 補償ストラテジー
解説 間接ストラテジー
大きく
- メタ認知ストラテジー
- 情意ストラテジー
- 社会的ストラテジー
に分けられます。
解説 メタ認知ストラテジー
自身の得意・不得意を把握して学習計画を立てる
などが該当します。
解説 情意ストラテジー
発表前に気持ちを落ち着かせる
などが該当します。
解説 社会的ストラテジー
母語話者の友人に質問する
図書館で勉強する
などが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
例文から文法規則を類推するのは、認知ストラテジーの内容です。
類型と例が一致しているので、1が正解です。
語呂合わせを考えるのは、記憶ストラテジーの内容です。
メタ認知ストラテジーではないので、2は間違いです。
分からない単語を別の言葉に言い換えるのは、補償ストラテジーの内容です。
社会的ストラテジーではないので、3は間違いです。
会話パートナー等の他者を学習に活用するのは、社会的ストラテジーの内容です。
情意ストラテジーではないので、4は間違いです。
問2 場独立型の学習者が得意とされること
解説 認知スタイル
さまざまな分類があり、令和3年度試験・平成30年度試験では今回と同じ「場独立型⇔場依存型」が出題されました。
解説 場独立型
第二言語習得においては、
全体の把握や他の要素との関連づけがなくても回答が出せる文法
などに強いとされています。
解説 場依存型
第二言語習得においては、
社会的スキル
文脈からの判断
などに強いとされています。




その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
自分から積極的に話しかけるような社会的スキルが得意なのは、場依存型の学習者ですね。
1は間違いです。
文章や会話の概要のような文脈からの判断が得意なのは、場依存型の学習者ですね。
2は間違いです。
口頭でのパフォーマンステストのような社会的スキルが得意なのは、場依存型の学習者ですね。
3は間違いです。
活用規則の文法テストのような文脈がなくても答えが出せるものが得意なのは、場独立型の学習者ですね。
4が正解です。
問3 総合型の学習者が好む学習活動の例
その答えになる理由


認知スタイルの「総合型」「分析型」は、初見でした。
参考になる文献も見つからなかったのですが、難しく考えずに「総合」「分析」という語から追っていけば問題なく解くことができます。
「総合」とは、個々別々のものを1つに合わせまとめることです。
また「分析」とは、ある物事を分解して、それを成立させている要素を明らかにすることですね。
選択肢を1つずつ見てみると…
複数のものをまとめているのは、4だけですね。
これが正解です。
問4 学習スタイルを広げていくよう働きかける例
その答えになる理由


「視覚型」「聴覚型」「運動型」「触覚型」という分類も、初見でした。
ただ、これも難しく考えなければ問題なく解くことができます。
学習スタイルを広げていくように働きかけるので、1番得意ではない内容をするように促すものを探してみましょう。
視覚型の学習者が得意なのは、「読む・書く」によるものです。
劇でせりふのある役を演じることで、「聞く・話す」という別の学習スタイルに踏み込むことができますね。
学習スタイルを広げることにつながるので、1が正解です。
聴覚型の学習者が得意なのは、「聞く・話す」によるものです。
交流会での会話で使うのは「聞く・話す」なので、別の学習スタイルではないですね。
学習スタイルを広げることにつながっていないので、2は間違いです。
運動型の学習者が得意なのは、「体を動かすこと」によるものです。
街頭インタビューで使うのは「体を動かすこと」なので、別の学習スタイルではないですね。
学習スタイルを広げることにつながっていないので、3は間違いです。
触覚型の学習者が得意なのは、「実際に触れること」によるものです。
料理の中で道具を使うのは「実際に触れること」なので、別の学習スタイルではないですね。
学習スタイルを広げることにつながっていないので、4は間違いです。
問5 学習ストラテジーを意識させることが重要である理由
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
認知資源の容量を増やすには、
- 同時に複数のタスクを入れないようにする
- ノートに書き出して、考えを外部化する
などが有効です。
ただし、学習において認知資源が多いに越したことはありませんが、学習ストラテジーを意識することとは関係ありません。
1は、学習ストラテジーを意識させることが重要である理由として不適当です。
学習ストラテジーは、学習をより深く・より効率的に行うために「個人が」取る方法のことです。
教師側から「記憶ストラテジーを活用するために、語呂合わせを使いましょう」と指示するのではなく、学習者側が「どうすれば、もっと記憶に残りやすくできるか…?」を考えた末に取る手段だと言えます。
「自律的」「多様な学習方法を選択」がピッタリ合いますね。
2は、学習ストラテジーを意識させることが重要である理由として最も適当です。
教師の働きかけによって他者と協同的に外国語を学ばせることは………困難ではないですよね?
これが難しかったら、複数名が参加するクラスでの日本語教育はハードルが高いことになってしまいます。
学習ストラテジーとも関係ないですね。
3は、学習ストラテジーを意識させることが重要である理由として不適当です。
学んだ言語の数が増えるにつれて、細かな学習内容をモニターすることは難しくなっていきます。
ただし、これは学習ストラテジーによるものではなく、単に認知資源の容量を使っているからですね。
4は、学習ストラテジーを意識させることが重要である理由として不適当です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら