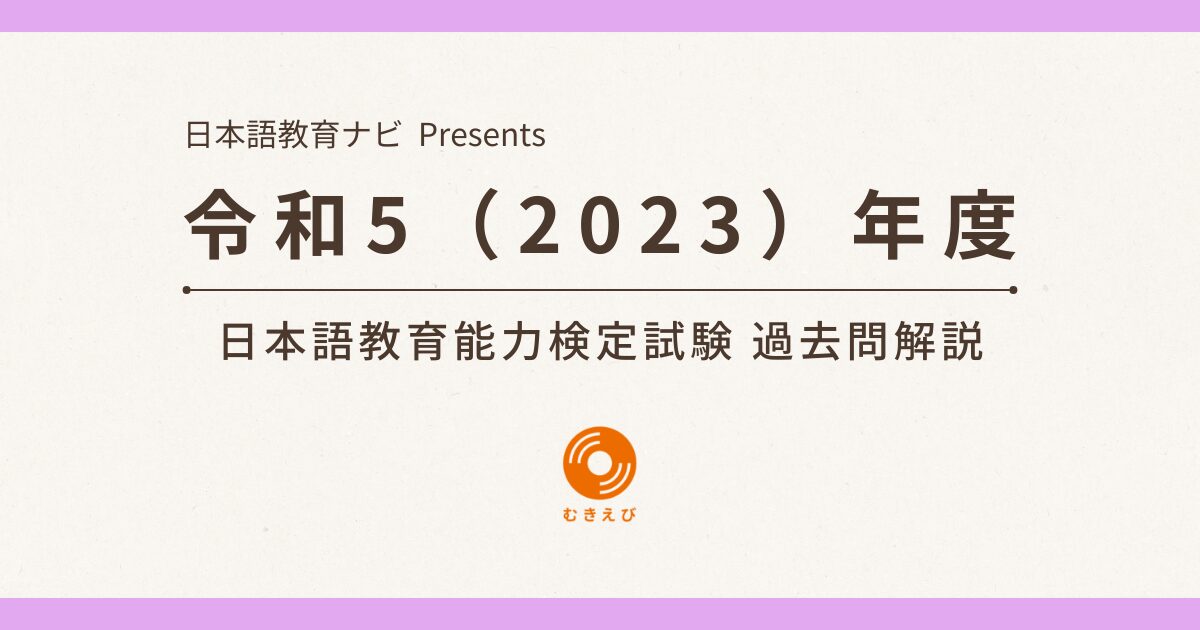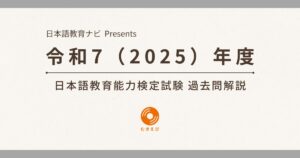令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題11
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 インプット
解説 インプット
解説 インテイク
その答えになる理由


インプットとインテイクは、どちらも情報を自身の頭の中に取り込む内容ですが、1番の違いは「取り込む情報にフィルタがかかっているか?」です。
インプットは、取り込む情報にフィルタをかけません。
昨日、駅前のカフェに行ってきたんだ。
という発話を聞いたら、それをそのまま情報として取り込みます。
インテイクは、取り込む際に情報にフィルタがかかります。
昨日、駅前のカフェに行ってきたんだ。
という発話を聞いたときに、「話し言葉だから『のだ』が『んだ』になっている」のように言語形式を意識したり、「駅前にカフェなんてあったっけ?」のように記憶のデータベースを探ったりするのがインテイクです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
末尾が
1 反応
2 データ
3 言語情報
4 プロセス
になっていますが、そこはポイントではありません。
「取り込む情報にフィルタがかかっているか?」で考えていきます。
「インターアクション」とは、学習者同士のやり取りのことです。
「やり取りを通じて気づいたこと」は、フィルタがかかった情報ですね。
インテイクの内容なので、1は間違いです。
そのままの状態ではなく言語形式に目を向けているので、情報にフィルタがかかっていますね。
インテイクの内容なので、2は間違いです。
音声だけ・記述だけに限定していないのは、フィルタがかかっていない情報ですね。
インプットの内容なので、3が正解です。
既知情報・新たな情報を区別しているので、情報にフィルタがかかっていますね。
インテイクの内容なので、4は間違いです。
問2 メンタル・レキシコン
解説 メンタル・レキシコン (心的辞書)
- 母語でも第二言語でも、覚えた単語は単語内・単語間で関連づけられ、音・意味・文法形式の3つからなる特徴の集合として保存されている。
- 保存のされ方は五十音順やアルファベット順でなく、常に情報の追加・更新を行っている。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
メンタル・レキシコンは、物理的な辞書のような五十音順やアルファベット順ではなく、常に情報の追加・更新が行われています。
1が正解です。
物理的な辞書でもメンタル・レキシコンでも、ある語についての「意味に関する情報」「言語形式に関する情報」は、区別して蓄積されています。
区別はされていますが、ある語を調べたときに「言語形式は●ページ・意味は▲ページ」となってはいないように書く情報の集合体として扱われるのも同じですね。
2は間違いです。
メンタル・レキシコンでは、母語でも第二言語でも、覚えた単語は単語内・単語間で関連づけられ、音・意味・文法形式の三つからなる特徴の集合として保存されています。
選択肢にあるのは、形態(文法形式)・意味・統語(文法形式)なので、特徴が1つ足りないですね。
音韻に関する情報も含まれるので、3は間違いです。
物理的な辞書では、情報が五十音順やアルファベット順に固定配列されています。
一方、メンタル・レキシコンでは、覚えた単語は単語内・単語間で関連づけられ、常に情報の追加・更新を行っているのが特徴的です。
このような配列の仕方・情報更新の違いはありますが、情報のあり方に違いはありません。
どちらであっても、「木」であれば「き」という音の情報・「木本の植物」という意味の情報・「木」という文法形式(言語形式)が載っていますね。
概略的な情報ではないので、4は間違いです。
問3 ネットワーク構造
その答えになる理由


単語と単語がどのように結びついているかを聞かれています。
メンタル・レキシコンの特徴を復習しておきましょう。
- 母語でも第二言語でも、覚えた単語は単語内・単語間で関連づけられ、音・意味・文法形式の3つからなる特徴の集合として保存されている。
- 保存のされ方は五十音順やアルファベット順でなく、常に情報の追加・更新を行っている。
物理的な辞書との違いは、五十音順やアルファベット順に単語が並んでいるわけではなく、何らかの要素で関連づけて整理されていることですね。
同義(同じ意味)・類義(似た意味)・異議(違う意味)のように意味で関連づけることもあれば、収める・治める・納める・修めるのように音で関連づけてることもあります。
また、墾田永年私財法は「聖武天皇の政治」「語呂の良い語」の2つの関連づけがされている…なんてこともありますね。
関連づけの方法は人それぞれですが、物理的な辞書のように五十音の順に基づいていることはありません。
3が正解です。
問4 プライミング効果
解説 プライミング効果
「ピザって10回言って」
「ピザ、ピザ…」
「(ひじを指して)ここは?」
「ひざ!」
は、プライミング効果を利用したものです。
「ひざ」を事前に刷り込まれたわけではないのですが、音の近似性から「ピザ→ひざ」が誘発されていますね。
プラスにもマイナスにも働くことがありますが、学習において期待されるのは「あらかじめ入った情報(プライム)により、その後の学習が効果的に進むこと」です。
その答えになる理由


「ドルチェ&ガッバーナの香水のせい」のように、何らかの刺激や与えられる部分的な情報によって感情や行動が動かされるのがプライミング効果です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は何も問題ありません。
これが正解です。
プライミング効果の引き金になるのは、何らかの刺激や与えられる部分的な情報です。
自身で分析したものは該当しないので、2は間違いです。
プライミング効果の引き金になるのは、何らかの刺激や与えられる部分的な情報です。
既に習得済みの母語の知識は該当しないので、3は間違いです。
プライミング効果の引き金になるのは、何らかの刺激や与えられる部分的な情報です。
先の内容の予測は該当しないので、4は間違いです。
問5 第一言語と第二言語の二つのメンタル・レキシコン
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
一般的に、概念と語彙では概念の方が多いと言われています。
「実際の試験で覚えた内容がそのまま出題されたときの脳内」「恋人がリボ払いを使っていると知ったときの感情」のように、単語にはなっていない概念もありますよね。
これは第一言語・第二言語に関係ない傾向なので、1は間違いです。
書字等の文字の形式に関する知識がどの程度共有されるかは、その言語で使われている文字次第です。
日本語と英語だと別物ですが、アルファベットを使う言語同士だと共有されている部分が大きいですね。
「二つの言語の間で共有されている」と言い切ることはできないので、2は間違いです。
日本語学習者が授業で意向形を習ったあとに「図書館に行こう」と誘われた場合…
「図書館に行く?と聞かれている」という言語学習と「行くor行かないのどちらにしよう…」という言語処理が同時に行われています。
第一言語だとほぼ言語処理のみですが、第二言語だと言語処理・言語学習が同時に起きることがありますね。
3は間違いです。
「新しい=できたり起こったりして間がない」は初級レベルの学習者でもわかりますが、「一環=全体としてのつながりを持つものの一部分」は上級レベルでないと難しいですね。
また、知ってはいても普段使わない語だと、語彙と概念の結びつきが弱くてパっと出てこない場合があります。
語彙と概念の結び付きの強さは習熟度の影響を受けるので、4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら