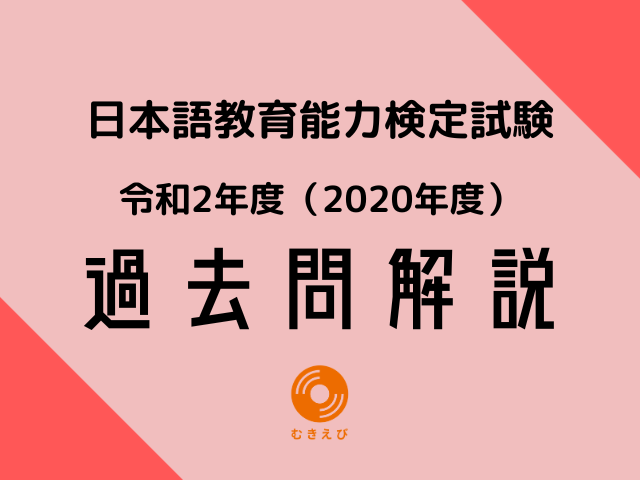令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題17
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


記述式問題の取り組み方
前提
試験Ⅲ自体は120分時間がありますが、記述式問題に当てられるのは20~30分程度です。
実施要項には書いていないので正しいかどうかは不明なのですが、試験Ⅲ記述式は
試験Ⅰ
試験Ⅱ
試験Ⅲマーク式
の総合得点が上位60%でないと採点されない…という話もあります。
試験の平均点等は、公益財団法人 日本語教育支援協会のHPで確認できるのですが
記述式を含む平均点等一覧は、マーク式による問題の総得点が上位である60%の人数の者についてのものである
日本語教育能力検定試験 結果の概要より
と記載があるためです。
「時間がなくて最後まで書ききれなかった」は絶対に避けるべきですが、「パニックになってマーク式がおざなりになってしまった」も採点すらされなかった…という結果にもなりかねません。
試験Ⅲマーク式は、試験Ⅰ・Ⅱと比べて平均点が高い傾向にあるので、取れる問題を落とさないようにしっかりと取り組んでいきましょう。
いきなり解答用紙に書き出さない
ここからが、記述式問題の取り組み方です。
小論文の取り組み方と同じですが、いきなり解答用紙に書き出すのはNGです。
まずは、以下を問題用紙の余白に書き出していきましょう。
① 何についての意見が求められているか?
② ①に対しての「自分の意見」「根拠」は何か?
③ ②に対しての「反対意見」「反対意見への配慮」は何か?
④ 段落構成と、各段落の内容を箇条書きで並べてみる。
イメージがつきづらいと思うので、実際に問題に取り組みながら解説していきます。
(あくまで、私の解答の作り方です。)
① 何についての意見が求められているか?
●言語サービスとしての「やさしい日本語」に関する取り組みに対しての批判について、日本語教育に関わる者としてどう思うか?
→ 賛成?反対?
●キーワードのいずれか1つ以上を使い、そのキーワードの意味を理解しているかがわかるように書く。
→ どれを選ぶ?ちゃんと意味わかってる?
が、今回求められている内容です。
文章にしてみると、シンプルですね。
問題文に線を引いても良いのですが、上記のように書き出してみるのがおススメです。
過去問に取り組むときも、赤本に取り組むときも、本番の試験のときも…記述式問題に取り組むときは「最初にこれをする」というルーチンを作ると、モードを切り替えることができます。
今回は、キーワードの選定も重要です。
個人的な難易度としては、
【易】複言語主義 →→→ 言語権 →→ 規範主義【難】
です。
一見、内容のわかりやすい「言語権」に飛びつきたくなってしまうのですが、用語の意味さえわかっていれば「複言語主義」が1番書きやすいと思います。
2つ以上使うことも問題ないのですが、ハードルがひどく上がるのでおススメしません。
危ない橋は渡らないでおきましょう。
各キーワードの内容は、以下の通りです。
解説 複言語主義
「複言語主義」とは、言語教育において、一個人が複数の言語を使えるが、その言語のレベルはその人の生活形態等によって差があっても良いとする考え方とのことです。
「CEFR」という、どの言語にも当てはまる言語能力の測定基準のベースになる考え方とされています。
似た語で「多言語主義」という言葉もあります。
「多言語主義」とは、ある社会において、どの言語を使っても不利にならないような社会を作り上げていくことを目指す考え方のことです。
「複言語主義」が個人の言語使用に関する考え方であるのに対し、「多言語主義」は社会における言語使用の考え方です。
解説 言語権(言語的人権)
「言語権(言語的人権)」とは、自ら望む言語を自由に使用できる権利のことです。
国連憲章や世界人権宣言にも明記されている権利であり、ある国や地域での少数言語話者が公用語・共通語を学ぶ機会を保障すること、かつ民族語を学び使用することを認めることを指すことが多いです。
解説 規範主義
「規範」という語の辞書的な意味は、のっとるべき規則・判断などの拠るべき手本や基準のことです。
直訳で考えれば、「規範主義」とは「ルールにのっとった考え方」となります。
※ 今回の問題では、制度(ルール)の意味だけでなく、「こうあるべき」という圧力も意味に含んでいると考えて良いと思います。
② ①に対しての「自分の意見」「根拠」は何か?
入社試験等であれば自身の本来のスタンスでいくべきですが、日本語教育能力検定試験のような場であれば「書きやすいスタンス」で良いと思います。
「書きやすい=ロジックを通しやすい」です。
私は、
● 批判に「反対」
● 理由は「外国人が日本で生活するためには、最低でも『やさしい日本語』レベルの日本語が必要だから」
で考えました。
実際には中立の意見であったり、どちらかと言えば…の意見であったりすることもありますが、どちらかに振り切った方が書きやすくなります。
③ ②に対しての「反対意見」「反対意見への配慮」は何か?
私が書くのであれば、反対意見の背景として「複言語主義」を登場させます。
「複言語主主義」は、 言語教育において、一個人が複数の言語を使えるが、その言語のレベルはその人の生活形態等によって差があっても良いとする考え方のことです。
「外国人が学ぶ日本語のレベルを勝手に決めるべきではない」という批判は、この複言語主義がベースになっています。
一方的に「反対」と述べるだけではロジックが補強できないので、
● 複言語主義の立場から、外国人が学ぶ日本語のレベルを勝手に設定すべきでないという批判は理解できる。
● 一方で、最低限のレベルを保障しなければ生活の場で困ってしまったり、日本人と同様の行政サービスが受けられなかったりと、外国人自身に不利なことが起きてしまう。
と展開させます。
④ 段落構成と、各段落の内容を箇条書きで並べてみる
「賛成」「反対」のタイプの問題であれば、2段落構成がおススメです。
1段落目
● …という批判がある
● 私は、この批判に反対だ
● それは、 外国人が日本で生活するためには、最低でも「やさしい日本語」レベルの日本語が必要だからだ
2段落目
● 複言語主義の立場から、外国人が学ぶ日本語のレベルを勝手に設定すべきでないという批判は理解できる
● 一方で、最低限のレベルを保障しなければ生活の場で困ってしまったり、日本人と同様の行政サービスが受けられなかったりと、外国人自身に不利なことが起きてしまうのも事実である
● だから、「やさしい日本語」での取り組みにより、外国人が日本で生活しやすい環境を作っていく必要があると考える。
解答用紙に書き出す前には、これくらいの粒度で情報を整理するのがおススメです。
ここまで来れば、あとは接続詞に気をつけてつないでいくだけです。
2段落構成の良いところは、
● ロジックがわかりやすいこと
(1段落目が、自分の意見 ⇔ 2段落目が、自分の意見への批判 など)
● 文章量のイメージがつきやすいこと
(半々を目安に書いていけばOK)
です。
ざっくりとした時間配分は、
● ①~④までの作業 15分
● 解答用紙への記入 10分
● 見直し 5分
のイメージです。
※ 脱字があった際は、全体を直すのではなく段落単位で修正するようにしましょう。
記述式問題は1回解いて終わりではなく、複数回取り組むのがおススメです。
やっていくうちに、やり方がパターン化できていきます。
今回であれば、賛成⇔反対・使うキーワードの選定を変えてもう1度取り組んでみましょう!