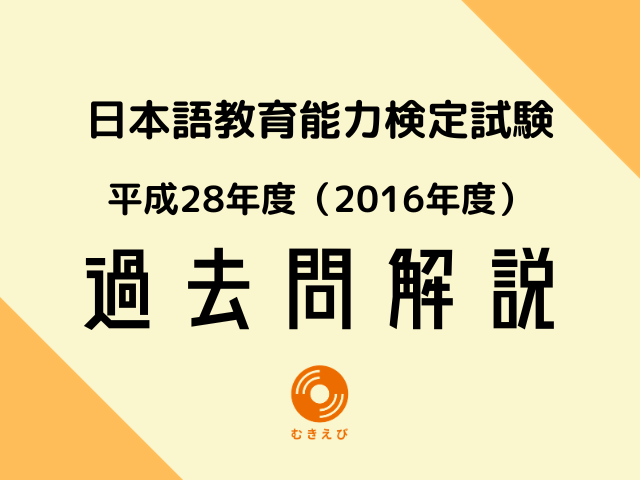平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題6
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 スキミング
問題6は、本文なしの「読解」に関する小問の集合体です。
用語の意味を確認しながら、1問ずつ進めていきましょう。
解説 スキミング
「スキミング」とは、読解や聴解において全体をざっと把握して大意をつかむことを指します。
細かい部分にこだわらず、ポイントを理解する力を養成するのが特徴です。
スキミングの力をつけることで、
●わからない部分を文脈から類推する
●先を予測しながら、読む・聞く
●仮説を立てて検証しながら、読む・聞く
といった活動ができるようになります。
解説 スキャニング
関連する用語もあわせて整理しておきましょう。
「スキャニング」とは、読解や聴解において特定の情報をつかむことを指します。
不要な部分を飛ばして、必要な情報のみを見つける力を養成するのが特徴です。
●求人情報から、希望する勤務地に関する情報を見つけ出す
●天気予報から、自分の住む地域に関する情報を聞き取る
などの活動ができるようになることを目的としています。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は「自分にあった日程と予算のツアー」という特定の情報を見つける活動なので、「スキャニング」の例です。
2は翻訳の内容なので、スキミングでもスキャニングでもありません。
3が「大意を把握する」なので、「スキミング」の例ですね。
これが正解です。
4は「因果関係を示す表現」という特定の情報を見つける活動なので、「スキャニング」の例です。
問2 ジグソー・リーディング
解説 ジグソー・リーディング
「ジグソー・リーディング」とは、読解練習の1つで、メンバーがそれぞれ異なった文章を読んで、自分が読んだ情報を持ち寄り、情報の断片から全体を作り上げ共有する活動のことです。
その答えになる理由


2が「ジグソー・リーディング」の内容そのままですね。
これが正解です。
問3 多読のルール
解説 多読
「多読」とは、大量に読むことで自然と語彙や文法の知識をつけていく活動のことです。
● 簡単な内容の本から始める
● わからないところは、辞書を引かずに飛ばして読む
● 途中で進められなくなったら、別の本を読む
などの注意点があります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
多読において、わからない単語は辞書を引かずに飛ばして読んでいきます。
1は間違いです。
多読では、学習者が無理なく読むことができる簡単な本から始めていきます。
2は間違いです。
多読では、途中で読み進められなくなったら別の本に切り替えを行います。
3が正解です。
多読では、わからないところがあったら、戻らずに読み飛ばして進めていきます。
4は間違いです。
問4 クローズテスト
解説 クローズテスト
「クローズテスト」とは、文章の中に空欄があり、そこに語を埋めていく問題のことです。
その答えになる理由


3が「クローズテスト」の内容そのままですね。
これが正解です。
問5 日本語能力試験の読解で出題される「統合理解」の説明
その答えになる理由


出典元はこちら
③ 関連がある複数のテキストを比較したり統合したりする問題
日本語能力検定試験 公式ウェブサイト 日本語能力試験ガイドブック詳細版 P35
一つのテキストを読み進めながら、内容的に関連がある他のテキストと関係づけ、共通点や相違点を比較したり、複数のテキストの内容を統合して理解したりすることも、読解の能力の一つです。このような「全体を迅速に読む/部分を注意深く読む」読み方(表10のAと D)を求める問題を、N1とN2で「統合理解」という新しい大問を立てて出題します。たとえば同じ話題について違う立場から書かれた二つのテキストについて、その違いや同じところが理解できるかを問います。
1が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら