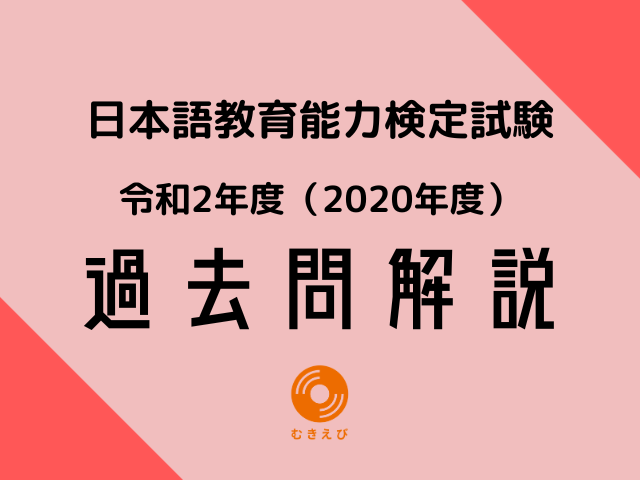令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題2
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 超分節的特徴
解説 超分節的特徴
語に付属して決まるアクセントや、文に付随して決まるイントネーションなどが例として挙げられます。
その答えになる理由


「一つ一つの単音を見ているだけでは捉えられない」から、超分節的特徴のことを述べていることがわかります。
1が正解です。
問2 無声区間
その答えになる理由


日本語の共通語において、調音法は、以下の6つです。
- 破裂音
- 摩擦音
- 破擦音
- 鼻音
- 弾き音
- 接近音
このうち無音区間がある(=溜めがある)のは、以下の3つです。
- 破裂音
- 破擦音
- 弾き音
選択肢の子音が含まれる音を見ていきましょう。
1で含まれる子音は、「み」の [m] です。
[m] 有声両唇鼻音 のため、無音区間が含まれていません。
2で含まれる子音は、「か」の [k] です。
[k] 無声軟口蓋破裂音 のため、無音区間が含まれていますね。
これが正解です。
3で含まれる子音は、「に」 の [ɲ] と「わ」の [w] ですね。
[ɲ] 有声(歯茎)硬口蓋鼻音・[w] 有声軟口蓋接近音のため、無音区間が含まれていません。
4で含まれる子音は、「ぬ」の [n] と「ま」の [m]ですね。
[n] 有声歯茎鼻音・[m] 有声両唇鼻音のため、無音区間が含まれていません。
問3 ポーズ
解説 統語
もうしあわせ
とポーズなしに一息に発音すると「申し合わせ」
もう・しあわせ
とポーズを置いて発音すると「もう幸せ」となるように、ポーズの位置によって、どのように語が結びついているかの統語構造を明確にすることができます。
その答えになる理由


1は、
- 東京にいる・友達のお姉さん
- 東京にいる友達の・お姉さん
のように、ポーズの位置によって表す内容が変わります。
「友達の」の後にポーズを置くことによって、東京にいるのが友達であることがわかりますね。
2は、
- 警官は必死に・逃げる犯人を追いかけた
- 警官は・必死に逃げる犯人を追いかけた
のように、ポーズの位置によって表す内容が変わります。
「警官は」の後にポーズを置くことによって、必死だったのが犯人であることがわかりますね。
これが正解です。
3は、
- 昨年・あの家を建てた建築士は引退した
- 昨年あの家を建てた・建築士は引退した
のように、ポーズの位置によって表す内容が変わります。
「建てた」の後にポーズを置くことによって、家を建てたのが昨年であることがわかりますね。
4は、
- この前・叔母からもらった桃を食べた
- この前叔母からもらった桃を・食べた
のように、ポーズの位置によって表す内容が変わります。
「桃を」の後にポーズを置くことによって、叔母から桃をもらったのがこの前であることがわかりますね。
問4 プロソディー
解説 プロソディー
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
ピッチパターンとは、周波数の形のことです。
日本語の共通語では、「大学の/友達と行く」を声に出したときのように、ひとかたまりのフレーズでピッチパタンが「へ」の字型になるという特徴があります。
1は、適当な内容です。
「火がつく」の「ひが」のアクセントは高低・「日が暮れる」の「ひが」のアクセントは低高ですね。
語の意味の区別にアクセントが影響しており、これをアクセントの弁別機能と言います。
2は、適当な内容です。
「おとうとは」のアクセントは、低高高高低ですね。
アクセント核である「おとうとは」の「と」は、ピッチ(高さ)が高いですが、前の音から特別大きく上昇するわけではありません。
3は、不適当な内容です。
「食べますか⤴」のように、発話末を上昇させることで疑問を表すことができます。
4は、適当な内容です。
問5 ポーズの入れ方
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
ポーズは、一定時間ごとではなく、適切なところで入れるように指導します。
1は、間違いです。
ピッチ(高さ)は、ポーズとは関係なく、語のアクセントによって違います。
2は、間違いです。
今日・の授業・で・は、「テイル形」・を勉強します。
のように、助詞の前でポーズを入れていたら……不自然ですね。
3は、間違いです。
ポーズの長さは、文と文の間であれば「短め」・段落と段落の間であれば「長め」が良いですね。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら