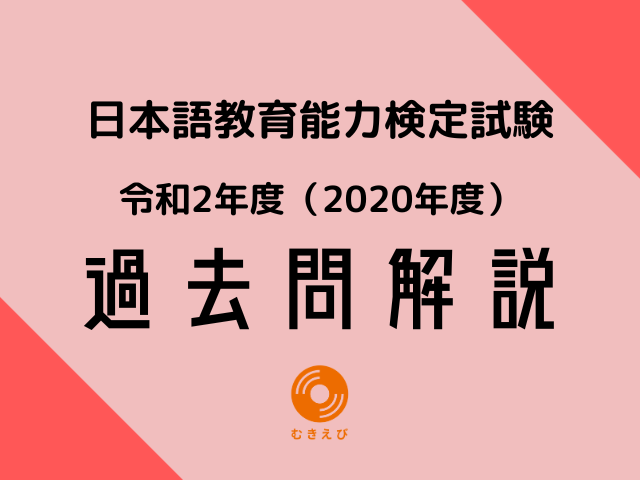令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題5
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案
その答えになる理由


出典はこちら
【基本的な考え】
「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案活用のためのガイドブック
・「生活者としての外国人」に対する日本語教育は,対話による相互理解の促進及びコミュニケーション力の向上を図り,「生活者としての外国人」が日本語を用いて社会生活へ参加できるようになることを目指すものです。標準的なカリキュラム案は,その日本語教育の具体的な内容やプログラムを検討・作成する際の基となるものです。
【内容】
・生活の基盤を形成する上で必要不可欠であると考えられる生活上の行為の事例,そこで必要となる日本語学習の項目・要素,関連する社会・文化的な情報などから構成されています。
【想定している利用者】
・各都道府県,市町村における日本語教育担当者等,各地域において日本語教育のコーディネーター的役割を果たす人に活用されることを想定しています。そのほかにも,各都道府県,市町村において,日本語教育施策や事業の企画を行う人や,教室活動を行う人などに利用されることを想定しています。
平成23年1月25日
文化審議会国語分科会
4がそのままですね。
これが正解です。
問2 モジュール型教材
解説 モジュール型教材
いつ授業に参加してもスムーズについてこられるように配慮されているので、仕事の都合等で毎回の授業参加が難しいビジネスピープルなどに適した教材です。
その答えになる理由


モジュール型教材がどのようなものかを知っていれば、他の選択肢を読まなくても答えにたどり着けます。
1が正解です。
どのような教材かの特徴を知らなくても、
module:システム・機械等を構成する単位(部分)
がわかれば、類推することもできますね。
問3
その答えになる理由


下線部Cにある通り、この授業の目標は、地震が起きた際に適切な行動がとれるようになることです。
STEP1では、地震について「感じたこと・考えていることを話し合う」
STEP2では、「具体的に考えたり・実物に触れる」
が挙げられています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、STEP1の「話し合い」の内容ですね。
これは、間違いです。
2は、STEP2の「具体的な考え・行動」に当たります。
これが正解です。
3の感想文を書くことは、STEP2の「具体的な考え・行動」から外れています。
これは、間違いです。
4の漢字の読み方を調べて共有することは、STEP2の「具体的な考え・行動」から外れています。
これは、間違いです。
問4 スキャニング
解説 スキャニング
- 求人情報から、希望する勤務地に関する情報を見つけ出す
- 天気予報から、自分の住む地域に関する情報を聞き取る
などの活動ができるようになることを目的としています。
解説 スキミング
スキミングの力をつけることで、
- わからない部分を文脈から類推する
- 先を予測しながら、読む・聞く
- 仮説を立てて検証しながら、読む・聞く
といった活動ができるようになります。
解説 ディクトグロス
- 教師が文章を読み、学習者はキーワードなどを聞き取ってメモを取る。
- メモをもとに、各自で聞き取った文章を復元する。
- グループで話し合いながら、元の文章を検討する。
- グループごとに、検討した内容を発表する。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、ディクトグロスの内容ですね。
これは、間違いです。
2は、大意を把握する活動であり、スキミングの内容ですね。
これは、間違いです。
3は、概要を把握する活動であり、スキミングの内容ですね。
これは、間違いです。
4は、特定の情報の把握する活動でありスキャニングの内容ですね。
これが正解です。
問5 対話中心の活動
解説 対話中心の活動
2つのポイントを意識しておきましょう。
1つ目は、ここでの「対話」とは
- 教師と学習者が対話する
- 学習者同士が対話する
ではなく、
- 同じ地域住民同士が対話する
ことを指していることです。
また、2つ目は、
- 授業の場面に限定した対話
ではなく、
- 人間関係を築く中での対話
を指していることです。
言葉をそのまま覚えなくても良いですが、対話の内容だけ押さえておくようにしましょう。
その答えになる理由


「学習者が自宅で必要な文型や単語を予習していること」を前提とするのは、反転授業の内容ですね。
通常の授業は、
授業 → 授業の内容を復習するための宿題
の順番ですが、反転授業では、
予習 → 予習してあることを前提にした授業
の順番になります。
対話とは関係ないため、1は間違いです。
2は、インタビュー形式になっており、対話ではありません。
3は、何も問題ありません。
これが正解です。
4は、対話の相手が違いますね。
「学習者同士」を対話として捉えてしまうと、間違いやすい選択肢かと思います。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら