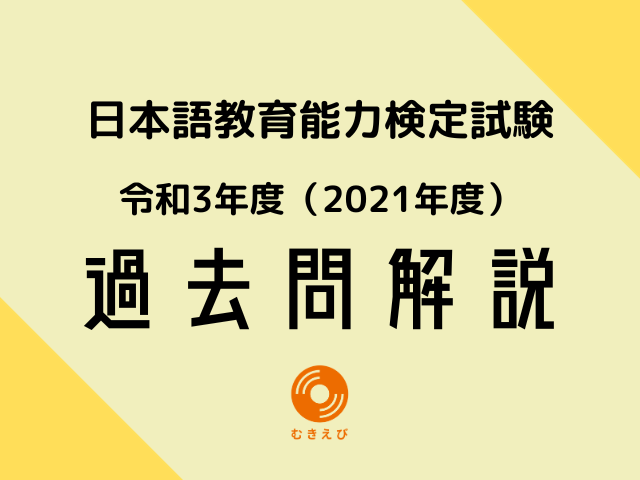令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題4
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 語と語の組み合わせが特別な慣用的意味を表す場合
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
気が短い
せっかちである
気が長い
あせらず、ゆったりとしている
「気が短い」「気が長い」ともに慣用的な意味を持っています。
1は間違いです。
手を切る
今までの関係を絶つ
手を焼く
取り扱いに困る
「手を切る」「手を焼く」ともに慣用的な意味を持っています。
2は間違いです。
襟を正す
心をひきしめ、真面目な態度になる
「襟を正す」は慣用的な意味を持っていますが、「襟を繕う」は慣用的な意味を持っていません。
3が正解です。
腕が鳴る
腕前をあらわそうとして、じっとしていられない
腕が立つ
すぐれた腕前・技量を持っている
「腕が鳴る」「腕が立つ」ともに慣用的な意味を持っています。
4は間違いです。
問2 どうやら
解説 推定のモダリティ
昨晩、雨が降ったようだ。
昨晩、雨が降ったらしい。
解説 様態のモダリティ
今にも雨が降りそうだ。
解説 照応
指し示す内容が前にある場合を前方照応・後ろにある場合を後方照応と言います。
【前方照応】
この人がAさんです。彼は、高校で英語を教えています。
【後方照応】
こんな話、聞いたことある?スマホがなかったころは…
解説 呼応
おそらく、彼は成功するだろう。
なぜ、宿題をやらなかったのですか?
その答えになる理由


「どうやら」を使って例文を作ってみましょう。
○ どうやら、私が最後だったようだ。
○ どうやら、私が最後だったらしい。
× どうやら、私が最後だった。
のように、文末に「ようだ」「らしい」が来ないと、文が不自然ですね。
この「どうやら → ようだ」「どうやら → らしい」のように、先行する語に応じて、後ろに特定の語形が来ることを呼応と言います。
また、「ようだ」「らしい」により、何らかの情報を頼りに「私が最後だった」ことを推測していることがわかりますね。
このように、ものごとの内容を推測して決定することを推定と言います。
(ア)に入るのが「推定」・(イ)に入るのが「呼応」なので、2が正解です。
問3
その答えになる理由


共起とは、1つの文や句の内部で、2つの別の語が同時に用いられることです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
【意志動詞】
○ 明日、ピクニックに行こう。
のように、意志動詞は、「~(よ)う」と共起して勧誘の意味を表せますが、
【無意志動詞】
× 雨が降ろう。
のように、無意志動詞は、そもそも「~(よ)う」と共起することができません。
1は、正しいです。
【自動詞】
ガラスが割れる。
↓
× ガラスが割れてある。
のように、自動詞は、そもそも「~てある」と共起することができません。
2は、間違いです。
【自動詞】
散歩の途中で雨が降った。
↓
私は、散歩の途中で雨に降られた。
【他動詞】
Aさんが私を殴った。
↓
私は、Aさんに殴られた。
のように、「~(ら)れる」により、自動詞・他動詞ともに迷惑の意味を表すことができます。
3は、間違いです。
【意志動詞】
雨が降る。
↓
雨が降ってしまった。
【無意志動詞】
花瓶を割った。
↓
花瓶を割ってしまった。
のように、「~てしまう」が後悔していることを表すのは、意志動詞と共起した場合に限られます。
4は、間違いです。
問4 使役を表す「~(さ)せる」
その答えになる理由


例文で考えてみましょう。
事前に記事を読ませる。
↓
事前に記事を読ませてある。
「~てある」と共起した「~(さ)せる」は、動きの結果の状態を表しており、経験の意味ではありません。
1は、間違いです。
Aさんにケガをさせた。
↓
Aさんにケガをさせてしまった。
「~てしまう」と共起した「~(さ)せる」は、責任感や後悔を表しており、強制の意味ではありません。
2は、間違いです。
部屋を掃除させる。
↓
部屋を掃除させられる。
「~(ら)れる」と共起した「~(さ)せる」は、迷惑や被害を表しており、放任の意味ではありません。
3は、間違いです。
自由に話し合いをさせる。
↓
自由に話し合いをさせてやる。
「~(ら)れる」と共起した「~(さ)せる」は、許可や許容の意味を表します。
4が正解です。
問5 多義語の意味の違い
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「なめる」のヲ格対象が
飴をなめる。
砂糖をなめる。
などのときは、「舌で触れる」の意味ですが、
練習をなめる。
試験をなめる。
などのときは、「軽くとらえる」の意味になります。
1は、多義語の意味の違いに関する記述として適当な内容です。
「ほめる」のヲ格対象が
子どもをほめる。
作品をほめる。
などのときは、「物事を良いものとして評価する」の意味であり、これは
態度をほめる。
性格をほめる。
であっても変わりません。
2は、多義語の意味の違いに関する記述として不適当な内容です。
「明るい」の修飾対象が
明るい部屋
などのときは、「光が十分に差している」の意味ですが、
明るい性格
明るい話題
などのときは、「陽気である」「将来の見通しについて楽観できる」の意味になります。
3は、多義語の意味の違いに関する記述として適当な内容です。
「重い」の修飾対象が
重い荷物
などのときは、「目方が多い」の意味ですが、
重い立場
重い責任
などのときは、「重要」の意味になります。
4は、多義語の意味の違いに関する記述として適当な内容です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら