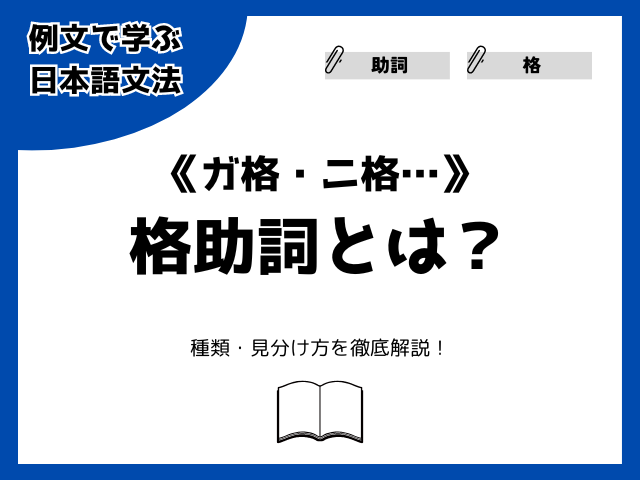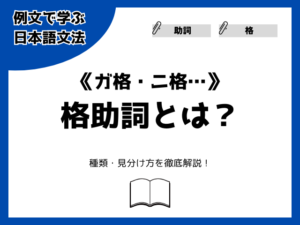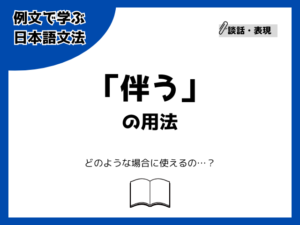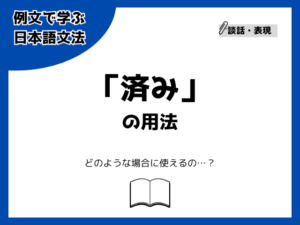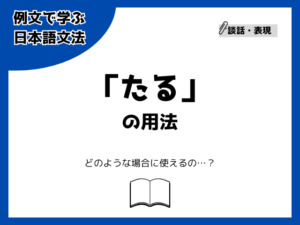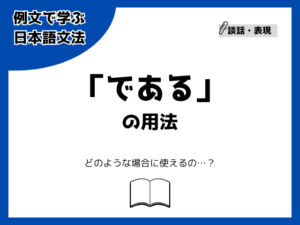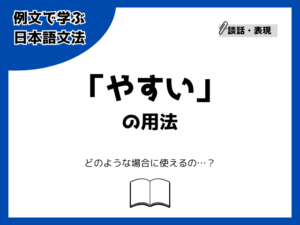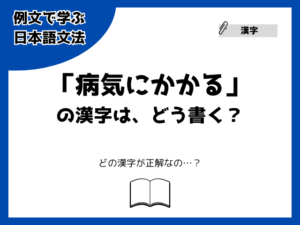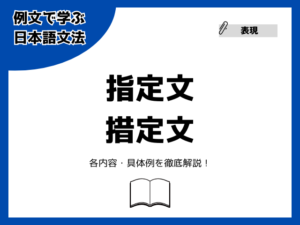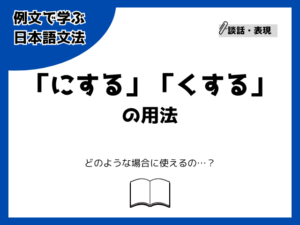今回は、
✅ 格助詞の種類
について、ゼロから一緒に勉強していきましょう。
この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。
例文で学ぶ 日本語文法
格とは?
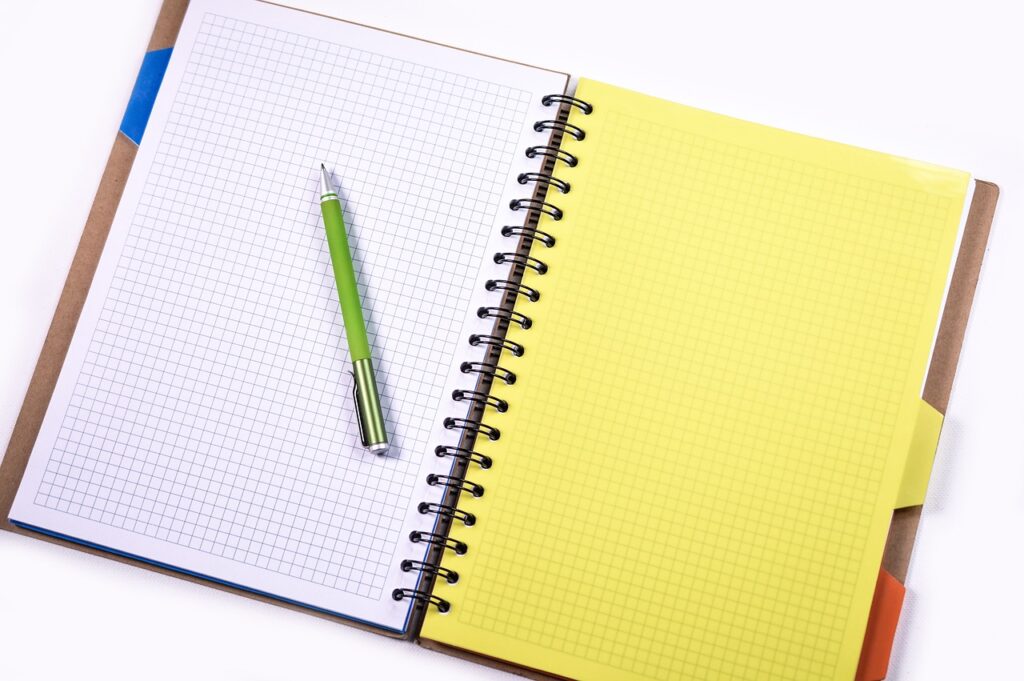
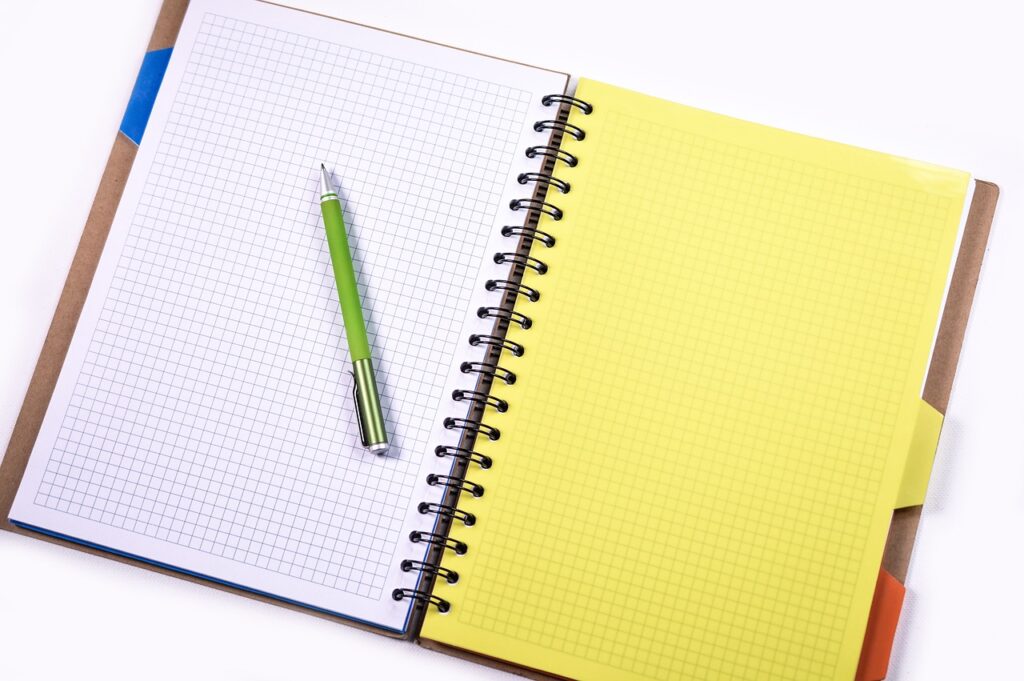
イメージがつきにくいと思うので、例文で見ていきましょう。
子どもたちが公園で遊んでいる。
この文の述語は、「遊んでいる」です。
誰が遊んでいるかというと…
子どもたちが公園で遊んでいる。
のように、「子どもたち」ですね。
「子どもたちが」の形で、述語「遊んでいる」という動きの主体を表しています。
また、どこで遊んでいるかというと…
子どもたちが公園で遊んでいる。
のように、「公園」ですね。
「公園で」の形で、述語「遊んでいる」という動きの場所を表しています。
「格」とは、名詞と述語の間に成り立つ意味関係を表す文法的手段のことです。
日本語の文には必ず述語があり、文中の名詞は述語との間に何らかの意味関係を持っています。
格助詞とは?
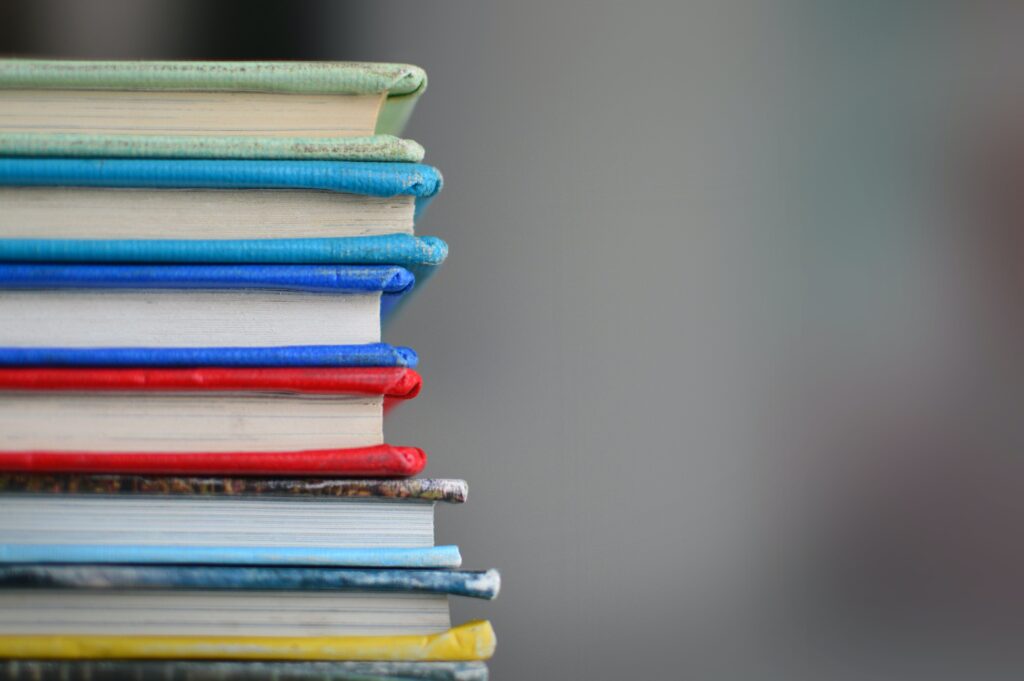
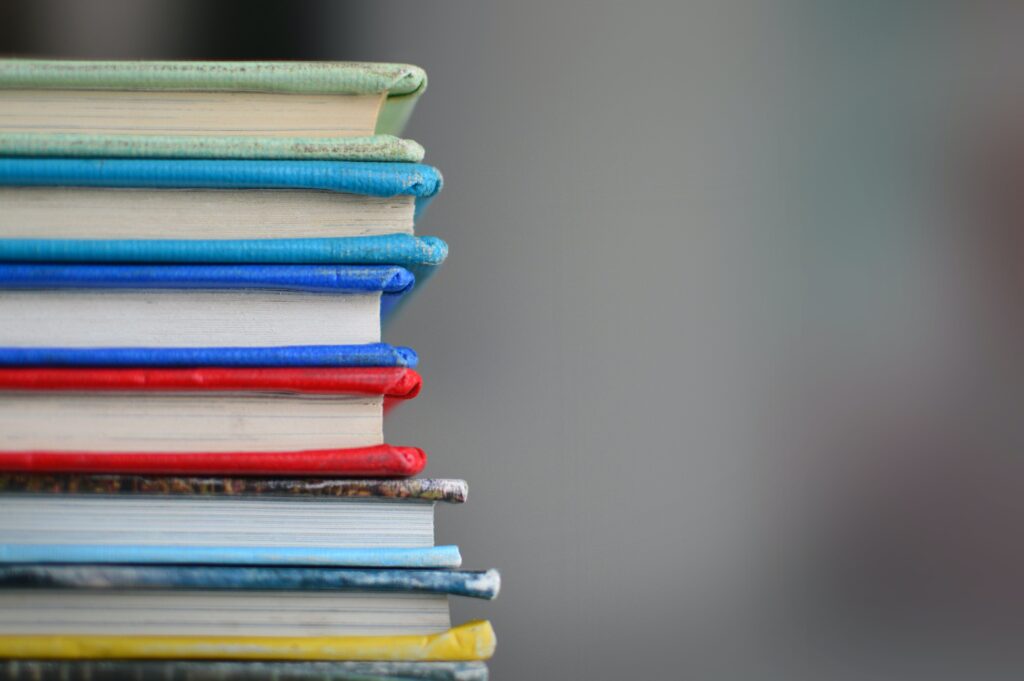
格助詞は、助詞の種類の1つ
子どもたちが 公園で 遊んでいる。
のように、「名詞+格助詞」の形で述語との意味関係を表します。
の順で見ていくことが大切です。
子どもたちが 公園で 遊んでいる。
であれば、
「遊んでいる」
「子どもたちが」
「公園で」
「子どもたちが」は、述語「遊んでいる」の動きの主体
「公園で」は、述語「遊んでいる」の動きの場所
となります。
助詞とは?
働け!
のように単独で用いられることもなければ、
働かない
働きます
のように活用することもありません。
カフェで働く。
カフェで働くので、良かったら来てね。
のように、名詞や動詞などにつく形で使用します。
ほかには、どのような助詞があるのか?
| 格助詞 | 名詞について、その名詞と述語との意味関係を表す |
| 連体助詞 | 名詞によって名詞を修飾するときに間に入る |
| 並列助詞 | 名詞と名詞を対等な関係で結びつける |
| とりたて助詞 | ほかの要素との関係を背景に、文中のある要素に焦点を当てて、累加・限定などを表す |
| 接続助詞 | 従属節と主節の関係を表す |
| 終助詞 | 文末に用いられ、事態に対する疑問や話し手に対する伝達の態度などを表す |
雨が降っているので、犬の散歩と買い物はやめておこうよ。
「が」は、格助詞です。
述語「降っている」という動きの主体が「雨」であることを表しています。
「ので」は、接続助詞です。
犬の散歩と買い物をやめておく理由が「雨が降っている」という事態であることを表しています。
「の」は、連体助詞です。
「犬」という名詞で「散歩」を修飾するために、間に入っています。
「と」は、並列助詞です。
「犬の散歩」と「買い物」を対等な関係で結びつけています。
「は」は、とりたて助詞です。
「ほかのことはするが、犬の散歩と買い物は…」という対比を表しています。
「よ」は、終助詞です。
「やめておこう」と言い切るのではなく、確認の意図が足されています。
助詞全般については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらも合わせてご確認ください。
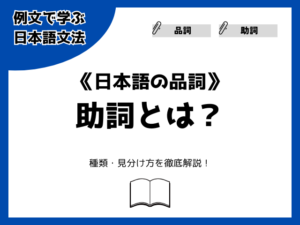
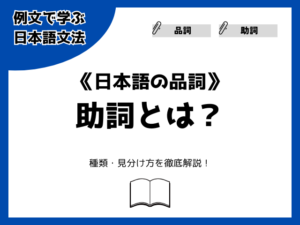
格助詞の覚え方
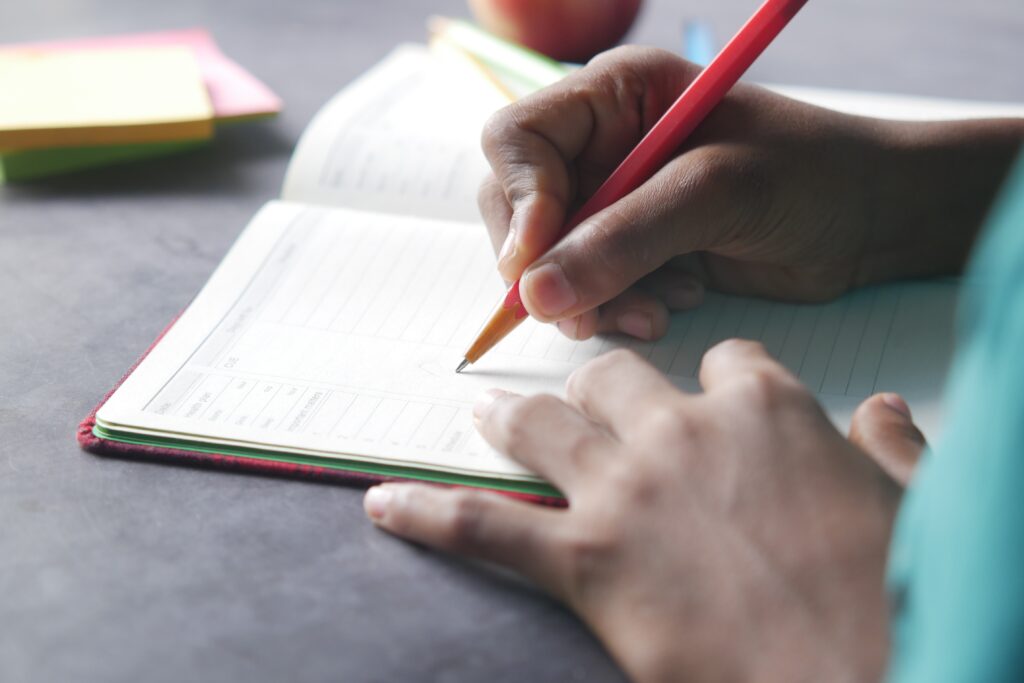
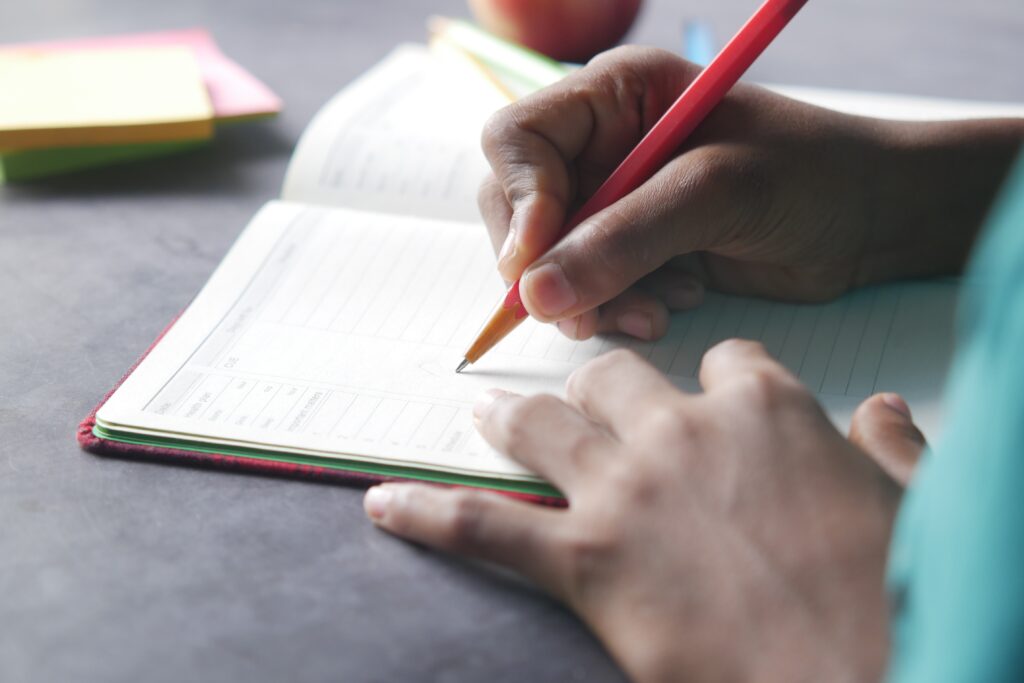
格助詞の内容を理解・暗記するためには、以下のステップを意識するようにしましょう。
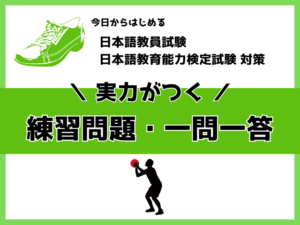
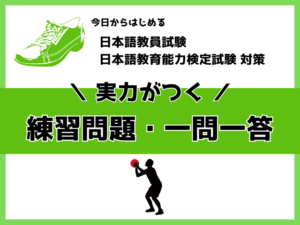
「用法」とは、使用の方法のことです。
料理を 祖母に 教わった。
- この場合の格助詞「を」の用法は、対象
- この場合の格助詞「に」の用法は、相手
のように、格助詞によって表すことができる意味関係が異なるため、用法も異なります。
まずは、それぞれの格助詞の用法を押さえていきましょう。
また、
10時に 駅前にある カフェに 着いた。
- 「10時に」の「に」の用法は、時
- 「駅前に」の「に」の用法は、場所
- 「カフェに」の「に」の用法は、着点
のように、同じ格助詞でも用法が異なる場合があります。
それぞれの格助詞の用法を押さえた上で、どの用法に当たるのかを見分けることが大切です。
また、格助詞は、●格という呼び方をすることがあります。
- 格助詞「が」 ⇔ ガ格
- 格助詞「を」 ⇔ ヲ格
- 格助詞「に」 ⇔ ニ格
- 格助詞「へ」 ⇔ へ格
- 格助詞「と」 ⇔ ト格
- 格助詞「から」 ⇔ カラ格
- 格助詞「より」 ⇔ ヨリ格
- 格助詞「で」 ⇔ デ格
- 格助詞「まで」 ⇔ マデ格
なので、どちらの呼び方が出てきても対応できるようにしていきましょう。
格助詞「が」の用法(ガ格)
格助詞「が」(ガ格)には、
- 主体
- 対象
の2つの用法があります。
①【動きの主体】
弟が駅まで迎えにいきます。
②【所有の対象】
私には、日本語教師になるという夢がある。
格助詞「を」の用法(ヲ格)
格助詞「を」(ヲ格)には、
- 対象
- 起点
- 経過域
の用法があります。
①【動作の対象】
文法を勉強した。
②【移動の起点】
最後に学校を出た。
③【空間的な経過域】
道の真ん中を通った。
格助詞「に」の用法(ニ格)
格助詞「ニ」(ニ格)には、
- 着点
- 相手
- 場所
- 起因・根拠
- 主体
- 対象
- 手段
- 時
- 領域
- 目的
- 役割
- 割合
の用法があります。
①【移動の着点】
駅に着いた。
②【授与の相手】
母に誕生日プレゼントをあげた。
③【存在の場所】
本棚に参考書がある。
④【感情・感覚の起因】
彼の考え方に親近感がわいた。
⑤【能力の主体】
彼にこの問題が解けるはずがない。
⑥【動作の対象】
父に反抗した。
⑦【手段(付着物)】
全身が毛におおわれている。
⑧【時(時点)】
3時に学校で集まりましょう。
⑨【認識の成り立つ領域】
私には、彼の考え方が革新的に思えた。
➉【移動の目的】
明日、買い物に行こうよ。
⑪【役割(名目)】
お礼にギフト券を贈った。
⑫【割合】
10人に1人が当選しています。
格助詞「へ」の用法(へ格)
格助詞「ヘ」(へ格)には、
- 着点
の用法があります。
①【着点(移動の方向)】
自転車で駅へ向かった。
格助詞「と」の用法(ト格)
格助詞「と」(ト格)には、
- 相手
- 着点
- 内容
の用法があります。
①【共同動作の相手】
友だちと買い物に行った。
②【着点(変化の結果)】
彼女は猛勉強の結果、日本語教師となった。
③【内容】
彼は、私にとって人生の師匠と言える。
格助詞「から」の用法(カラ格)
格助詞「から」(カラ格)には、
- 起点
- 主体
- 起因・根拠
- 経過域
- 手段
の用法があります。
①【範囲の起点】
5ページから10ページまで読んできてください。
②【動きの主体】
田中さんには、私からお伝えしておきますね。
③【判断の根拠】
特徴的な話し方から、彼だとわかった。
④【空間的な経過域】
虫が窓から入ってきた。
⑤【手段(構成要素)】
この参考書は、練習問題と解説から成り立っている。
格助詞「より」の用法(ヨリ格)
格助詞「より」(ヨリ格)には、
- 起点
の用法があります。
①【範囲の起点】
5ページより先を読み進めていってください。
格助詞「で」の用法(デ格)
格助詞「で」(デ格)には、
- 場所
- 手段
- 起因・根拠
- 主体
- 限界
- 領域
- 目的
- 様態
の用法があります。
①【動きの場所】
図書館で勉強した。
②【手段(道具)】
スコップで穴を掘った。
③【判断の根拠】
後ろ姿で彼女だとわかった。
④【動きの主体】
チームでこの問題に取り組んだ。
⑤【範囲の上限】
先着50名で締め切ります。
⑥【評価の成り立つ領域】
エベレストが世界で1番高い山だ。
⑦【動作の目的】
日本には観光で来ました。
⑧【動きの様態】
はだしで走り回った。
格助詞「まで」の用法(マデ格)
格助詞「まで」(マデ格)には、
- 着点
の用法があります。
①【着点(範囲の終点)】
10ページまで勉強を終えた。
格助詞の用法を見分ける練習問題にチャレンジ!
| 格助詞「が」の用法 | 主体、対象 |
| 格助詞「を」の用法 | 対象、起点、経過域 |
| 格助詞「に」の用法 | 着点、相手、場所、起因・根拠、主体、対象、手段、時、領域、目的、役割、割合 |
| 格助詞「へ」の用法 格助詞「まで」の用法 | 着点 |
| 格助詞「と」の用法 | 相手、着点、内容 |
| 格助詞「から」の用法 | 起点、主体、起因・根拠、経過域、手段 |
| 格助詞「より」の用法 | 起点 |
| 格助詞「で」の用法 | 場所、手段、起因・根拠、主体、限界、領域、目的、様態 |
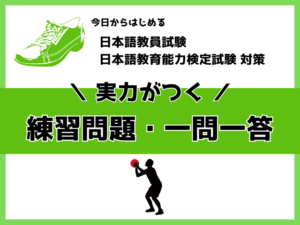
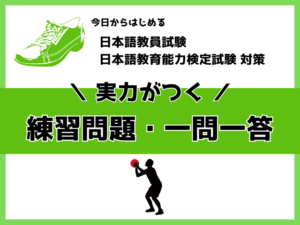
参考書籍
今回は、
- 格とは?
- 格助詞とは?
- 格助詞の覚え方
- それぞれの格助詞の用法
について、解説してきました。
を主に参考にしています。
さらに詳しく勉強したい方は、ぜひ手に入れてみてください。
また、この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、ブックマークしてご確認ください。