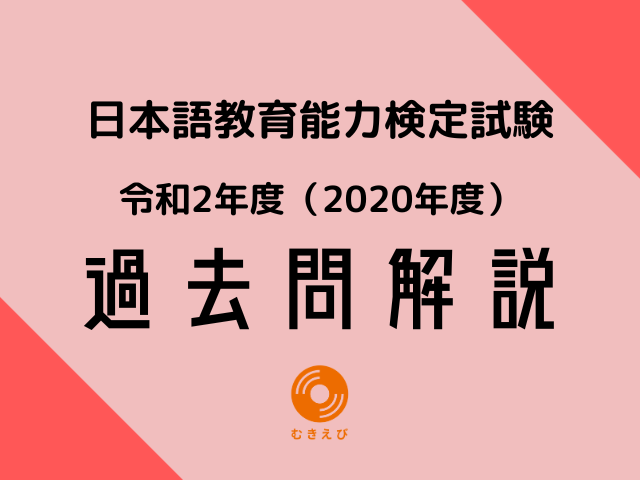令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題1
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
(1)調音点
日本語教育能力検定試験のトップバッターの問題は、例年「音声記号」です。
これは、私が過去問を持っている「平成26年度試験」から変更ありません。
試験Ⅰ 問題1は、【 】に示した観点から見て他と性質の異なるものを選ぶ問題です。
(1)であれば、今回の【調音点】以外にも、子音では【調音法】・母音では【唇のまるめ】などが出題されています。
まずは、用語の確認からしていきましょう。
解説 調音点
声道で鼻腔への通路を開閉したり、舌や唇を動かしたりして、声道の形などを変え様々な言語音をつくることを「調音」と言います。
● 両唇
● 歯茎
● 硬口蓋
などの調音を行う器官が調音点です。
解説 調音法
関連する用語も合わせて整理してしまいましょう。
呼気を妨害して子音を調音するときの方法を「調音法」と言います。
日本語の子音は
① 声帯振動の有無 (無声音・有声音)
② 調音点 (どこで)
③ 調音法 (どのように)
の3点の組み合わせで音が決まります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
.png)
.png)
1 [θ] 無声歯摩擦音
2 [m] 無声両唇鼻音
3 [b] 有声両唇破裂音
4 [ɸ] 無声両唇摩擦音
5 [p] 無声両唇破裂音
[θ] のみ、調音点が「歯」ですね。
1が正解です。
日本語の子音にはない音で、think [θɪŋk] などが該当します。
日本語にない子音ばかりが出題される…ということはないので、全ての選択肢がわからなくても、消去法で解くことができるタイプの問題です。
また、この [θ] は平成28年度試験でも出題されています。
(そのときは、誤答の選択肢の1つでした。)
過去問で取り組んだ年度の誤答が、今回の正答…というのはよくあるパターンです。
誤答の選択肢の内容も、合わせて覚えてしまいましょう。
(2)ガ行音
「ガ行」が出題されたときに真っ先に疑うのは、「鼻濁音になっていないか?」です。
解説 鼻濁音
「鼻濁音」とは、鼻音化された濁音のことで、通常は有声軟口蓋鼻音で発音される [ŋ] を指します。
「鼻濁音」になるのは、
- 語中・語尾
- 助詞の「が」
- 連濁になる場合
- 「小学校」のような結びつきの強い語中
です。
「連濁」とは、
長靴(ながぐつ)
日差し(ひざし)
のように、2つの語が結びついて1語になる際に、後ろの語の頭の清音が濁音になる現象のことなので、あわせて覚えておきましょう。
ガ行の音は、
がっこう
[ɡ] 有声軟口蓋破裂音
のように、語頭では [ɡ] で発音されますが、
はがき
[ŋ] 有声軟口蓋鼻音
のように、語中では鼻濁音の [ŋ] で発音されます。
調音点が破裂音・鼻音で違いますね。
口腔断面図で表すと、


[ɡ] 有声軟口蓋破裂音
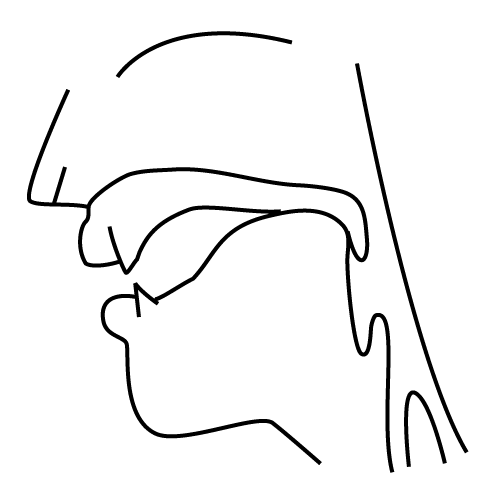
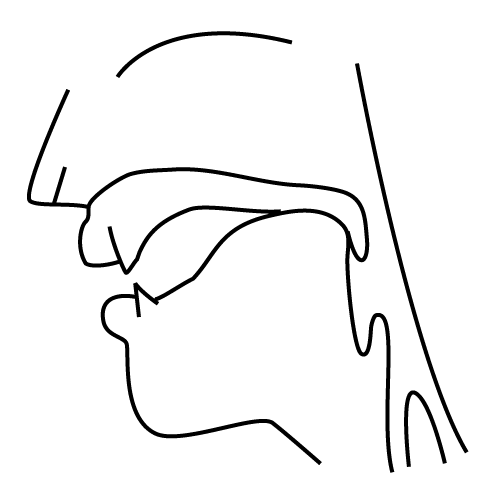
[ŋ] 有声軟口蓋鼻音
のように、鼻腔への通路が開いている・開いていないという違いがあります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 かいごし
2 ぎじゅつしゃ
3 だいがくせい
4 しゅげいてん
5 かぐや
2のみ、語頭で「鼻濁音」になっていません。
これが正解です。
(3)アクセントによる弁別
解説 アクセントの弁別機能
あめ
という語だけでは、「雨」「飴」のどちらを指しているかがわかりませんが、
あめ(高低)
であれば、「雨」であることが
あめ(低高)
であれば、「飴」であることがわかりますね。
解説 アクセントの統語機能
語の切れ目がどこにあるのかを判断できるのは、アクセントの統語機能によるものです。
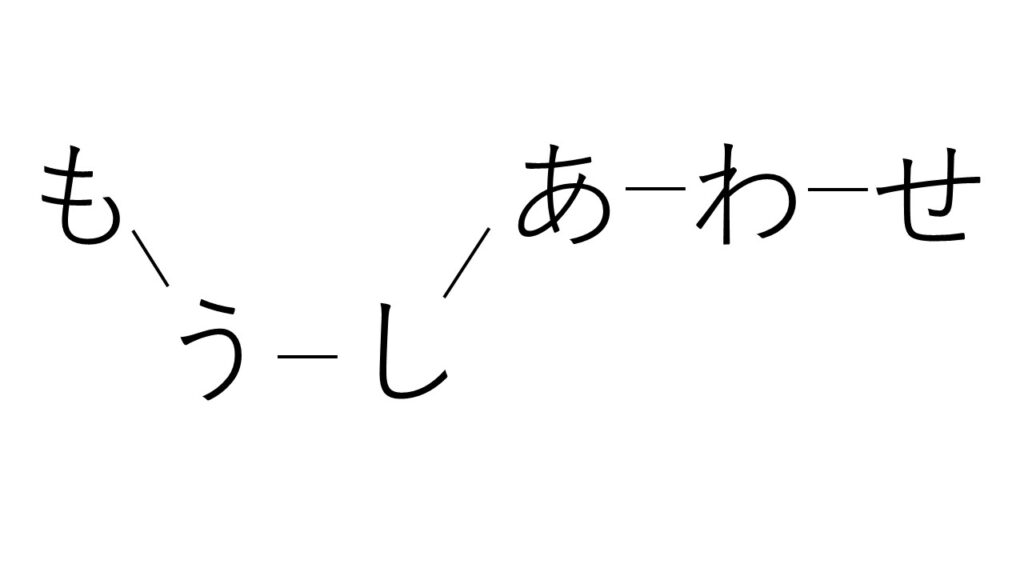
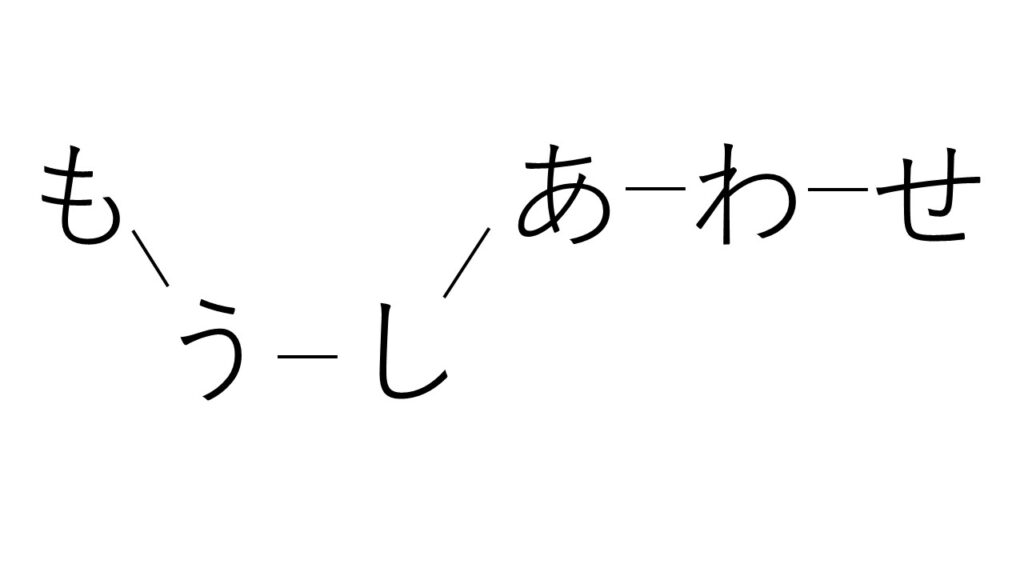
もう幸せ
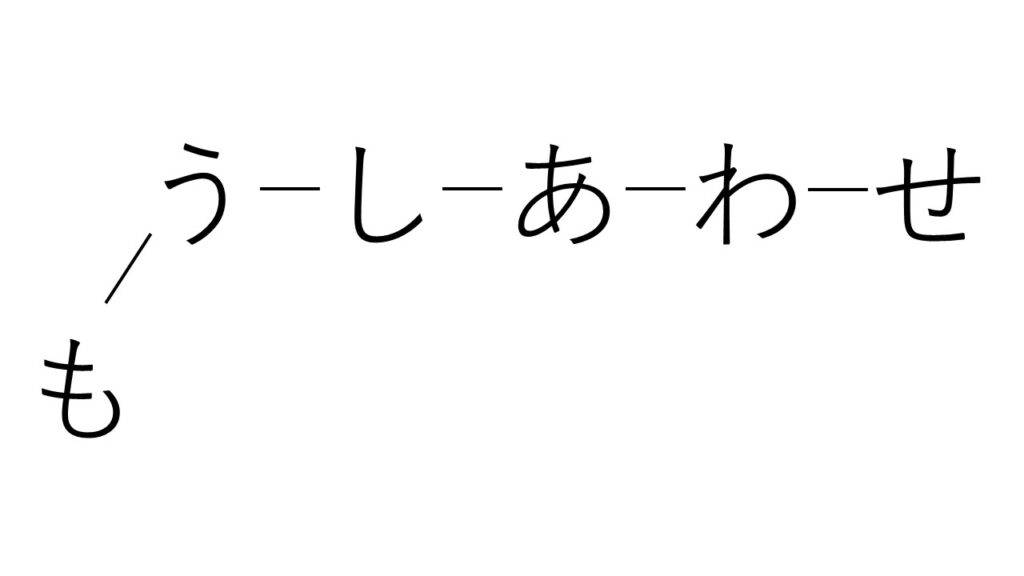
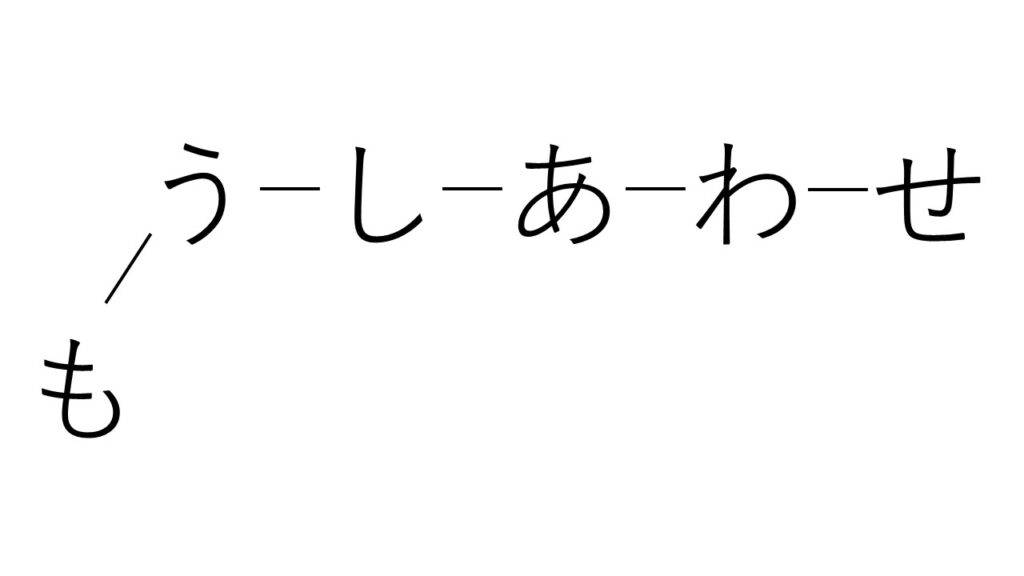
申し合わせ
アクセントによって、「どこまでが一語か?」を判断できますね。
上の例だと、左が「もう+幸せ」の2語・右が「申し合わせ」の1語です。
その答えになる理由


2語なので、アクセントは
- 平板式ー平板型 (低高)
- 起伏式ー頭高型 (高低)
のどちらかです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
柿(低高)
下記(高低)
のように、「かき」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。
橋(低高)
箸(高低)
のように、「はし」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。
空き(低高)
秋(高低)
のように、「あき」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。
石(低高)
医師(高低)
のように、「いし」は、アクセント型によって語の弁別が行われています。
風(低高)
風邪(低高)
のように、「かぜ」は、アクセント型による語の弁別が行われていません。
5が正解です。
(4)音便
解説 音便
どの音に変化するかによって
- イ音便
- ウ音便
- 撥音便
- 促音便
に分類することができます。
【イ音便】
書く → 書いて
【ウ音便】
ありがたく → ありがとう
【撥音便】
飛ぶ → 飛んで
【促音便】
蹴る → 蹴って
以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
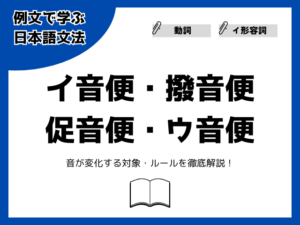
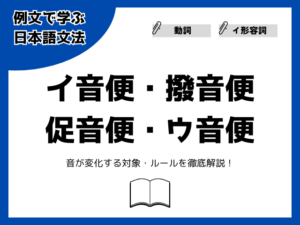
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
書く → 書いた
1は、タ形にしたときにイ音便が現れます。
蹴る → 蹴った
2は、タ形にしたときに促音便が現れます。
話す → 話した
3は、タ形にしても音便が現れないですね。
これが正解です。
住む → 住んだ
4は、タ形にしたときに撥音便が現れます。
洗う → 洗った
5は、タ形にしたときに促音便が現れます。
(5)音読みの種類(漢音・唐音)
解説 漢音
人材(じんざい)
尽力(じんりょく)
終日(しゅうじつ)
解説 唐音(宋音)
呼び鈴(よびりん)
金子(きんす)
布団(ふとん)
その答えになる理由


選択肢の漢字の読み方は以下の通りです。
| 呉音 | 漢音 | 唐音 | |
| 力 | リキ | リョク | – |
| 子 | シ | シ | ス |
| 期 | ゴ・ギ | キ | – |
| 文 | モン | ブン | – |
| 下 | ゲ | カ | – |
2のみ「唐音」、そのほかは「漢音」ですね。
2が正解です。
音読みの種類である呉音・漢音・唐音については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
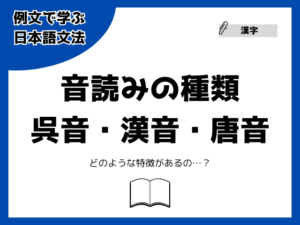
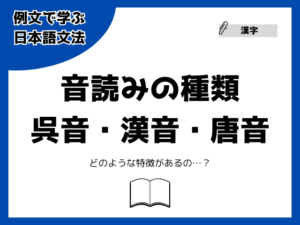
(6)異字同訓
解説 異字同訓
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
切る
斬る
のように、「切」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。
興す
起こす
のように、「興」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。
採る
取る
のように、「取」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。
収める
納める
のように、「収」には、同じ訓を表す異なる漢字があります。
届く
のように、「届」には、同じ訓を表す異なる漢字がありません。
5のみ、同訓異字がないですね。
これが正解です。
(7)心理動詞の格
解説 格
イメージがつきにくいと思うので、例文で見ていきましょう。
子どもたちが公園で遊んでいる。
この文の述語は、「遊んでいる」です。
誰が遊んでいるかというと…
子どもたちが公園で遊んでいる。
のように、「子どもたち」ですね。
「子どもたちが」の形で、述語「遊んでいる」という動きの主体を表しています。
また、どこで遊んでいるかというと…
子どもたちが公園で遊んでいる。
のように、「公園」ですね。
「公園で」の形で、述語「遊んでいる」という動きの場所を表しています。
「格」とは、名詞と述語の間に成り立つ意味関係を表す文法的手段のことです。
日本語の文には必ず述語があり、文中の名詞は述語との間に何らかの意味関係を持っています。
解説 心理動詞
喜ぶ
心配する
あこがれる
などが該当します。
その答えになる理由


「心理動詞の格」という文法用語に面食らってしまいますが、「選択肢の心理動詞は、それぞれどの格助詞が必要か」というだけの問題です。
例文で考えてみましょう。
私は、彼の行動にあきれている。
心理動詞「あきれる」は、対象に二格をとります。
私は、彼が改心するのをあきらめた。
心理動詞「あきらめる」は、対象にヲ格をとります。
私は、彼をしたっている。
心理動詞「したう」は、対象にヲ格をとります。
私は、彼をうたがっている。
心理動詞「うたがう」は、対象にヲ格をとります。
彼をうやまうのも、もっともだ。
心理動詞「うやまう」は、対象にヲ格をとります。
1のみ、対象が二格で表されますね。
これが正解です。
格助詞全般については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
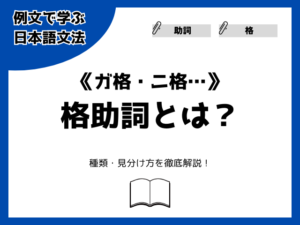
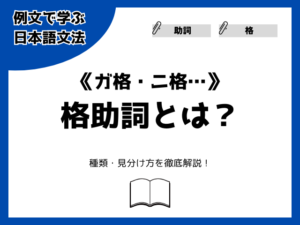
(8)ニ格名詞句の意味
その答えになる理由


格助詞「に」(ニ格)は、格助詞の中でも1番用法の種類があり、大きく
- 着点
- 相手
- 場所
- 起因・根拠
- 主体
- 対象
- 手段
- 時
- 領域
- 目的
- 割合
の12個に分けることができます。
以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。
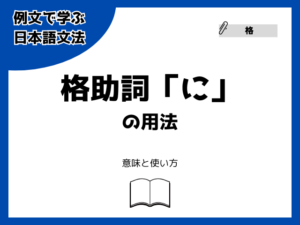
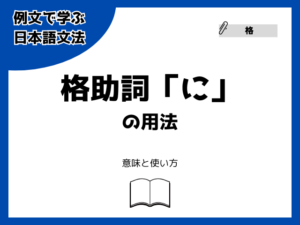
今回の問題では、12個の用法のうち「着点」と「相手」が出てきています。
「着点」とは、物事の移動を伴う動作において、その移動が終わる位置のことです。
子どもが公園に着く。
泥がズボンに着く。
「相手」とは、事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物のことです。
Aさんに話しかける。
指名手配犯が警察に捕まった。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の「小林さん」は、「習う」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。
この場合のニ格は、相手の用法です。
2の「山田さん」は、「借りる」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。
この場合のニ格は、相手の用法です。
3の「鈴木さん」は、「教わる」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。
この場合のニ格は、相手の用法です。
4の「田中さん」は、「田中さんのところ」を表しているので、有情物ではないですね。
財布の移動先なので、この場合のニ格は、着点の用法です。
5の「小川さん」は、「もらう」という事態の成立に関与する、主体以外のもう一方の有情物ですね。
この場合のニ格は、相手の用法です。
(9)「とても」の意味
状態副詞
先生がいきなり話し出した。
では、どのように先生が話し出したかを
息子の肩にそっと手を置いた。
では、どのように息子の肩にを置いたかを詳しく説明していますね。
雷がピカッと光った。
のような擬音語や
赤ちゃんがにこにこ笑っている。
のような擬態語も情態副詞に分類されます。
程度副詞
この漫画は、かなり面白い。
では、その漫画がどれくらい面白いかを
もっとゆっくり話してください。
では、話すスピードをどれくらいにしてほしいかを詳しく説明しています。
陳述副詞
おそらく、雨が降る( )。
「おそらく」を見て、自然と
おそらく、雨が降るだろう。
という推量の表現が頭に浮かぶのではないでしょうか?
このように、上に一定の語があるときに、下にそれに応じる語形を要することを「呼応」と言います。
たとえ失敗しても、決してあきらめない。
であれば、
- 陳述副詞「たとえ」により、「ても」という仮定の表現が呼応
- 陳述副詞「決して」により、「ない」という否定の表現が呼応
していますね。
なお、陳述副詞は、あくまで「述語の陳述の仕方を表す副詞」です。
句末・文末と呼応することが多いのですが、
この点数であれば、きっと合格できるよ。
明日は、きっと来てください。
のような呼応する語がない場合もあります。
その答えになる理由


2は、「つまらない」の程度がはなはなだしいことを表していますね。
これだけ、程度副詞です。
そのほかは、後ろに否定の語が来ており「とても~できない」という不可能を表しています。
これらは、陳述副詞です。
副詞については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
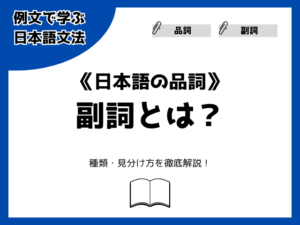
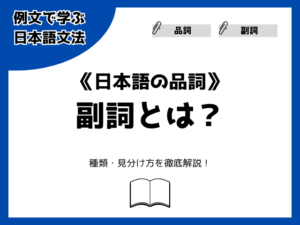
(10)肯定否定の対立
その答えになる理由


「肯定否定の対立」とあると難しく感じてしまいますが、選択肢を否定形に変えてみると簡単です。
1 挨拶しません
2 訪問しません
3 連絡しません
4 失礼しません(?)
5 面会しません
「失礼します」で1つの慣用表現になっているので、否定形にすると不自然になってしまいますね。
4が正解です。
(11)「てくる」の用法
解説 「~てくる」の用法
【空間的用法】
彼が自転車でやってきた。
→ 移動してきたのは、「彼」
結婚式の招待状が送られてきた。
→ 移動してきたのは、「招待状」
彼がたくさんの本を持ってきた。
→ 異動してきたのは、「彼」と「本」
【時間的用法】
留学生が増えてきた。
→ 時間の流れとともに…
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「トラック」と「荷物」が移動してきています。
これは、空間的用法です。
2は、「お客さん」が移動してきています。
これは、空間的用法です。
3は、「私」と「お弁当」が移動してきています。
これは、空間的用法です。
4は、「米」が移動してきています。
これは、空間的用法です。
5は、何かが移動してきているのではなく、時間と共に状態が変化しています。
これだけ、時間的用法です。
(12)条件節の意味
その答えになる理由


条件節には、ざっくりと
- 確定条件 … 確実に起こる内容(ほか確実に起こるとは限らない条件(他の選択肢もある)の選択肢はない)
- 仮定条件 … 確実に起こるとは限らない内容(ほかの選択肢もある)
があります。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の「明日になる」は、確実に起こりますね。
これは、確定条件の内容です。
2の「1,000円出す」は、ほかの選択肢にすることもできますね。
これは、仮定条件の内容です。
3の「タクシーに乗る」は、ほかの選択肢にすることもできますね。
これは、仮定条件の内容です。
4の「この本を読む」は、ほかの選択肢にすることもできますね。
これは、仮定条件の内容です。
5の「こちらの道を行く」は、ほかの選択肢にすることもできますね。
これは、仮定条件の内容です。
(13)身体部位を含んだ表現の意味
その答えになる理由


これはサービス問題ですね。
1 比喩表現で、実際に「腹を割っている」のではありません。
2 比喩表現で、実際に「口を挟んでいる」のではありません。
3 比喩表現ではなく、実際に「足を洗って」います。
4 比喩表現で、実際に「手を出している」のではありません。
5 比喩表現で、実際に「耳を貸している」のではありません。
3が正解です。
(14)ト格の意味
その答えになる理由


格助詞「と」(ト格)には、大きく
- 相手
- 着点
- 内容
の3つの用法があります。
以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。
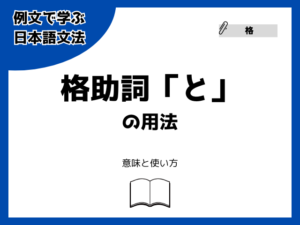
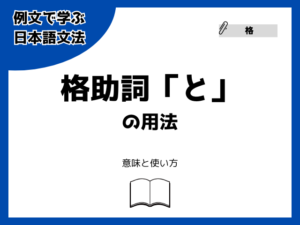
今回の問題は、「相手」の用法をさらに細分化していますね。
相手の用法は、
① 共同動作の相手
Aさんと図書館で勉強をした。
② 相互動作の相手
Aさんと口喧嘩をした。
③ 基準としての相手
Aさんとカバンの趣味が合う。
の3つに細分化することができ、各選択肢は、①②のいずれかに分類することができます。
「① 共同動作の相手」は、1人でもできる動作を誰かと行っています。
Aさんと図書館で勉強をした。
であれば、「Aさんと」を除いても文が成立しますね。
「② 相互動作の相手」は、誰かと一緒でないと動作が成立しません。
Aさんと口喧嘩をした。
であれば、「Aさん」を取り除くことができないですね。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の「見た」は、1人でも動作が成立しますね。
この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。
2の「楽器を弾いた」は、1人でも動作が成立しますね。
この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。
3の「歌った」は、1人でも動作が成立しますね。
この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。
4の「飲んだ」は、1人でも動作が成立しますね。
この場合のト格は、「① 共同動作の相手」の用法です。
5の「けんかをした」は、1人だと動作が成立しないですね。
この場合のト格は、「② 相互動作の相手」の用法です。
(15)直示表現(ダイクシス)
解説 直示表現(ダイクシス)
これが私の新しい自転車だ。
と言われたときに、発話の現場にいないと「自転車」がどれを指しているかがわからないですね。
また、
2日後までに、この仕事を終えてください。
も、発話の現場にいないと「2日後」がいつを指すのかがわかりません。
これらの場合の「これ」「明日」は、直示表現(ダイクシス)にあたります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の「こちら」が指しているのは、発話側です。
現場にいて、どちらの発話化がわからないと、どちら側を指しているのかがわからないですね。
これは、直示表現(ダイクシス)です。
2の「後ほど」は、発話のタイミングによって、いつを指すかが変わりますね。
発話の現場にいないと内容がわからないので、直示表現(ダイクシス)です。
3の「そこ」は、文脈から「駅」だと判断できます。
現場にいなくても内容がわかるので、直示表現(ダイクシス)ではありません。
4の「今週」は、発話のタイミングによって、いつを指すかが変わりますね。
発話の現場にいないと内容がわからないので、直示表現(ダイクシス)です。
5の「川の向こう側」は、話し手がどちら側にいるかによって、指す場所が変わりますね。
発話の現場にいないと内容がわからないので、直示表現(ダイクシス)です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら